 |
 |
 |
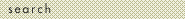 |
 |
|
|
 |
パフォーマー
|
 |
会場
|
 |
 |
公演日
|
|
| 大阪物語 |
松岡永子 |
女優二人による未知座アトリエでの公演。久しぶりの書き下ろしはさすがアングラ正統派の貫禄。エネルギーの充満した極端に密度の高い芝居。 インターネットラジオからハム無線まで、あらゆる時代のあらゆる電波が飛び交う宇宙。シェークスピアの古典英語から大阪のおばちゃんのおしゃべり、韓国語、手話まであらゆる言葉が飛び交う舞台。あらゆるコミュニケーションが飛び交い、それでもなお「理解のために充分」な言葉があるとはいえない世界。
溢れる形而上学的な言葉はわからせるためのものではないのだろう。あらゆる言葉を尽くし、尽きたところに顕れるはずの完璧な沈黙、人知を越えた沈黙。言葉は、そんな沈黙への供物なのではないか。以前どこかで目にした、音楽は人の奏でる美しい音と神の美しい無音(という音)とが同時に響いて始めて音楽になるのだ、といった理論を思い出した。
そんな舞台を言葉で語ろうとするのはあまりに無粋である。なによりもわたしの能力を超えることだ。だからたった一つ、一番印象に残っているビジュアルについてだけ書き留めておきたい。全部は部分の寄せ集めだが全体はどんな小さな部分にも反映する、という言葉(誰の言葉だったっけ)を頼りに、最も小さな細部にも全体が表れることを期待して。 おばちゃんの買い物かごから取り出される豆腐と薄揚げ。どちらもあまりに見慣れていてあまりじっくり見たことのないもの。それを見詰める。
「薄揚げの上にのせられた豆腐」。
この「豆腐」はもちろん、その「角に頭をぶつけ」るためのものだ。「薄揚げ」は「お稲荷さんではなく地蔵さんにお供えするときには『黄金の草履』と言う」と意味づけられたものだ。その「豆腐」を「薄揚げ」の上にのせる。それを大阪城に見立てたり…通常の意味、特殊な意味、この場でしか流通しない意味…幾重にも意味を背負ってそこにある「豆腐」と「薄揚げ」は、でも豆腐と薄揚げなのだ。 存在は意味に還元し尽くせない。 これは結局、この二人の役者の存在で成立する舞台なのだなあと思う。それは達者な唄やタップダンスのレベルの高さゆえではない。言葉を重ねていけばいくほど、意味を重ねていけばいくほど、「存在」が露わになっていく。存在を支えられるだけの強度を持った役者があってはじめて可能な舞台だ。
二時間半の舞台だが、一度見て充分とは思えないのか、二回三回と見に来ているリピーターがたくさんいた。
|
|

 |
|