|
|
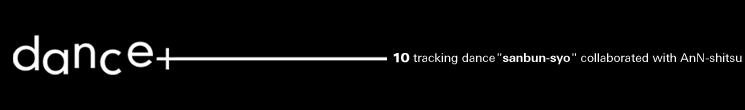 |
| AnN-shitsu presents シキのコンクリート《散文抄》 2005年11月05日-06日
築港赤レンガ倉庫315
|
|||
作品レビュー《散文抄》#01
ピアノがひとつきり置かれたがらんとした空間をまず埋めてゆくのは、奥行きの3分の1ほどにしつらえられた客席に座をとる観客だ。
そこから段差なくつづく上演空間は、むき出しの電灯で、ぼんやりと明暗の領域を分けている。やがて演奏家が登場してピアノに向かう。彼女の視線が待ち望まれて登場したダンサーに注がれ、その集中が観客のと束ねられたとき、最初の一音が奏でられる。 こんな風に始まる第1部は、4名のダンサー(東野祥子、山本泰輔、黒子さなえ、木村英一)が順に、波多野敦子の演奏に絡めるように展開する即興演技を焦点としている。その間、一時もダンサーから目を反らすことはできない。もちろん、なにもない空間で動く物体が、観客の視線を独占する唯一のオブジェとなるからではない。踊りがすごいのだ。けれども、ここでそのすごさについて、ダンサーの技術的な確かさや演技力、相貌が備える魅力を云々するのでは感じが伝わりにくい。それでは、踊り手の中にあれやこれやの特性がとじ込められており、見る者は自分の体を忘れ、目だけでそれに相対しているみたいではないか。だが、見ることと同時にわたしは動いている。この実感にしたがうなら、運動する感じを見る者の身体に引き起こしたということが、ダンサーの能力、あるいは仕事に帰せられるべきだろう。 |
|||
ここでの踊り手たちの仕事を説明するのに、ちょうどその衣装を思い浮かべてもらえばいい。ダンサーの体に見事にまとわりついていた田川朋子デザインの衣装のように、わたしたちの視線は動きに一歩先んじようとし、しかしほとんど遅れてついてゆく。つまり、ダンサーたちが動くにつれて、ともに空間を移動してまわるかのように思われる観客の視線は、一定のずれに隔てられているのだ。そのときわたしは動きを先取りする意識、あるいは予期に導かれているようだ。一般に、予期はなんらかの筋道-ここでは動きが描く軌跡から抽象される論理のようなもの-があって生みだされる。 めくらめっぽうに空間をかき回す手からは何も伝わってこないことと比べてみても、『散文抄』の出演者たちは、即席で反応としての運動を産みだしているのではなく、この筋道を小刻みに操っているように見受けられる。ふつうダンスを見ていると、筋道をすっかり先取りしてしまうことが結構あって、そうすると視線の運動は滞る。してみれば、視線が一時も停滞しない、つまりダンスから目が離せないということは、このダンサーたちは動きの筋道を刻々と更新して、観客の予期を誘い出しつつ裏切るということを同時に行っているのではないだろうか。そのためには、踊る者の身体は見る者の身体と絶対的に違う秩序を備えていなければならないだろう。この隔たりは、観客の視線をダンサーの動きや身体の表面に留めおくだけでは決してない。そこから繰り出される踊りを追うことで、見る者の目や身体の構えまでも、秩序を新たにされるような感覚を覚えるのではないか。 text by メガネ(log osaka) photograph by 井上嘉和 |
|||
| < back | next
> |
||
|
Copyright© log All Right Reserved. |
|||