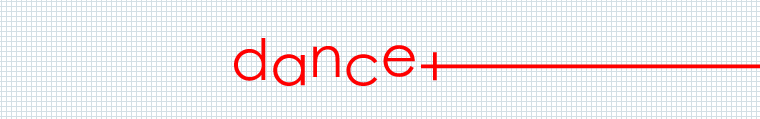| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
文・写真
+ dance+編集委員会
 |
dance+とは
ダンスを楽しむ研究サークル。情報編集のほか、ドキュメント、ビデオ鑑賞会などをとおして、ダンスと地域、ダンスと生活をつなぎます。
- 古後奈緒子(メガネ)
窓口担当。守備範囲は前後100年ほど。
- 森本万紀子
エンタメ担当。
- 森本アリ
音楽家/ガラス職人/グラフィックデザイナー/DJ/家具職人/映画助監督/大家/自治会会長/NPOスタッフなど。
- 神澤真理 NEW!
日常の中にある「おもしろそう」を発掘中。
記事へのご意見、ご感想、上記活動への参加に関心をお持ちの方はこちらへ→ danceplus@gmail.com
|
|
|

|