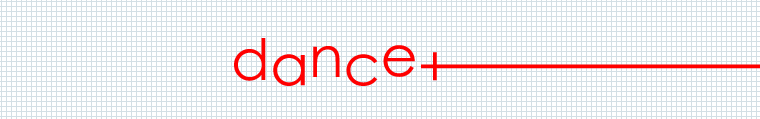| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
文・写真
+ dance+編集委員会
 |
dance+とは
ダンスを楽しむ研究サークル。情報編集のほか、ドキュメント、ビデオ鑑賞会などをとおして、ダンスと地域、ダンスと生活をつなぎます。
- 古後奈緒子(メガネ)
窓口担当。守備範囲は前後100年ほど。
- 森本万紀子
エンタメ担当。
- 森本アリ
音楽家/ガラス職人/グラフィックデザイナー/DJ/家具職人/映画助監督/大家/自治会会長/NPOスタッフなど。
- 神澤真理 NEW!
日常の中にある「おもしろそう」を発掘中。
記事へのご意見、ご感想、上記活動への参加に関心をお持ちの方はこちらへ→ danceplus@gmail.com
|
|
|
|
劇場を『ノリコボレル』双子の未亡人増殖計画
@Art Theater dB (Dance Circus38) 2007年7月5日
Text:メガネ
Photo:阿部綾子
2人のダンサーを構成単位とする 双子の未亡人が、50名のパフォーマーを擁した作品を発表した。スペクタクルを成立させる。あるいは集団を組織する。いずれの点から見ても、この増殖計画は一見無茶な思いつきのように思われた。だが、空間の特性とそこに集う人の関係を、創作の主要なファクターとしてきた彼らである。構想は必然的なものであり、結果として、今年なくなってしまったものたちを記憶にとどめる一作が生み出された。
|

| | |
|
作品タイトルともなった「ノリコボレル」とは、方言で「あふれ出す」の意だという。50名という数は、この言葉のイメージと、上演された劇場、Art Theater dBの舞台容量から具体的に導きだされた。もちろん、この小さな劇場の空間枠を物理的に脅かすことは、構想の一端でしかない。そこでねらいとされたのは、50人が生み出す空間が、劇場という枠組みや、そこでダンスに関る人の心の敷居を「ノリコボレ」てゆくことではなかったか。問題は、下手をすればマスゲームかまとまりを欠いた群衆に陥りかねない人数のパフォーマーたちを、どのように関係づけ、その関係にいかに観客を巻き込むかである。
方法上の特徴を見るために、先日他界したモーリス・ベジャールの『ボレロ』に先に触れておきたい。規模やコンテクストを度外視してこの作品を引き合いに出すのは、同じ音楽作品を使用していることを手がかりに、両者の構成上の違いを明らかにするためだけではない。その違いが、ダンスを成立させるために補い合う二つの力を象徴的に示していると思われるからだ。
両作品が基づく音楽作品『ボレロ』(モーリス・ラヴェル作曲)は、オーボエのソロに演奏楽器がどんどん参加してゆくことで、音の厚みを増してクライマックスに至る構成を持つ。故ベジャールは、この楽曲進行に合わせて、ダンスが身体の一部から劇場全体へと感染してゆく様を振付けで体現した。このとき感染源は、卓越した技術と演技により、見る者の欲望をかき立てる一人のダンサーである。舞台中央に位置するこのダンサーを見ることにより、彼/彼女の体が刻む振動を共有する者の輪は同心円状に広がり、実際には体を動かさない観客をも巻き込んでゆく。このような構成と舞踊家の力によって、20世紀の舞台舞踊のマスターピースは、踊る者と見る者の間に自然発生的に共同体を形成する舞踊の力を見事に表した。
対して双子の未亡人の『ノリコボレル』では、楽曲の『ボレロ』は中盤で音の足し算を止め、主旋律を交錯させながら引き算へと折り返す。さらに、踊る集団の中心となるべき役割にある佐伯有香と荻野ちよは、最後にちょろっとしか登場しない。優れた踊りを目にして皆が踊りの境地に導かれるという物語も、当然ながら書き換えられる。
舞台に乗ったパフォーマーたちは、集めも集めたり50人。背格好も年齢も、もちろんダンス経験もまちまちだ。わざわざ個性など引き出さなくとも均質化しようのないこの一群に、パフォーマーとしてのまとまりを与えるのは、テクニックや振りや拍節ではなく、共通のタスクと身体や視線への意識である。背中の方向に人にぶつからずに歩く。間隔を詰めて後ろにいる人の膝に腰掛ける(集団空気椅子!?)。抑えた照明からこの瞬間ぱっと明るくなったのをきっかけに、彼らは誰かに向かって声を出さずにしゃべりかけながら、再び空間に散らばる。シンプルなタスクとともに集合離散を繰り返す前半で、彼らの意識は内から外へ、自分から他の存在へと開いてゆくように見える。その頂点は、全員が他を押しのけながら客席に向かって話しかけ、一丸となってわっと両手を広げる瞬間だ。
このような流れは、本公演が初舞台、それどころか初の劇場体験といった者まで含む参加者を、パフォーマーとしての出発地点に立たせる優れた仕掛けであると同時に、舞台に足を踏み入れる者の意識の変化に添った物語ともなっている。興味深いのは、このようなパフォーマーの“誕生”の物語において、視線の果たす役割が際立たせられている点だ。例えば前半における意識の転換は、照明が明るくなったのと同時にもたらされた。後半では、パフォーマーが群衆の視線に要請されるといった関係が、もっとあからさまに示される。そこでは経験のあるダンサーによるソロと数名によるユニゾンの振付けが踊られているが、彼らを除く全員が、この“ダンス”には目もくれず、何もしていない一人のパフォーマーを見詰めて祭り上げるのだ。こんな風にパフォーマンスの成り立ちにおける視線の力を見せつけられると、前半の終わりに客席に向けられた全開の演技の片棒を担いでいたのは、その時客席に座っていたわたしたちなのかと思い至る。
|
以上のように、『ノリコボレル』は、踊る者と見る者の共犯関係に、巨匠が遺した『ボレロ』とは逆の視点から光をあてて見せた。それは、この関係において浮かび上がる視線を予め組織した場としての、劇場の重要性をも示唆する。その意味で本作は、コンテンポラリー・ダンスを見るために劇場に足を運ぶ観客層を形成して来たこの劇場の節目となる、フェスティバルゲートでの「ダンスサーカス」の締め括りにふさわしい。それは、ダンサーと観客と裏方が頻繁に入れ替る、この不思議な舞台空間に上がる最後の機会を多数の人間に提供したというだけではない。居合わせた者全てを劇場とそこに関る人の物語に巻き込む、周到に構想された記念アクションだったのである。
間近の双子情報
<ブック・アンデパンダン展〜たったひとつの、私の本〜>にて、双子の未亡人によるギャラリーパフォーマンス<アフタヌーン双子in芦屋>が行われます。
2007年12月22日(土)14:00/16:00〜@ 芦屋市立美術博物館
詳しくは双子の未亡人ウェブサイトへ>>> http://chamber.lomo.jp/futago/
|
|
|

|