 |
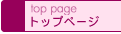 |
 |
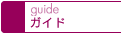 |
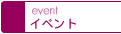 |
 |
| Books Archivesは「声」をキーワードに現代文学への開かれたアプローチを試みるウェブ放送アーカイヴです |
|
|
 |
 |
 |
| |
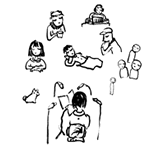 |
Books
Archives Vol.4
「吹雪の星の子どもたち」山口泉著(径書房刊/1984)から
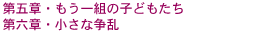
隣のお金持ちクラスの級長パリートを中心としたクスクス笑いの中、
ゴルノザ先生は、「体内脳」と「星外脳」という聞き慣れない言葉を口にします。
これから始まるのは、子どもたちが「星外脳」を手に入れるための旅だと。
その時突然、名流夫人の叱責の声が聞こえてきます。どうやら、遅刻してきた子どもがいるようです。老駐在も加わって、騒ぎがどんどん大きくなっていきました。
|

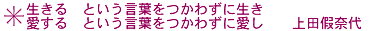
昨年4月にスタートし、まもなく1年をむかえるブックスアーカイブス。
毎週月曜の夜は公開朗読録音会となり、しずかな時間がながれる。
わたしは隔週で「吹雪の星のこどもたち」(山口泉著)を朗読している。
長編の本書は、地球ではない「吹雪の星」の小さな村を舞台に
チエーロ少年の目をとおした特別な一夜の出来事がおさめられている。
この村は地球上には存在しない。
けれど、日本のあるどこかの地域の物語として読みとかれるものだと、わたしは思う。
さまざまな大人たちの思惑が倫理の欠如とともに社会のゆがみとなり
チエーロは泡立つような息苦しさをとらえる。
何も発言してゆくことのできない弱者の立場でありながら
それでも、「生きる」ことにたちむかうチエーロやこどもたち、
貧しくともいのちの尊厳を大切にする大人たちに
わたしは何度も勇気づけられた。
はじめてこの本にであうとき、ノンブルのない扉に
序詞(歌う宝石の歌)に目をとめる。
生きる という言葉をつかわずに生き
愛する という言葉をつかわずに愛し
そして
そこに姿を映されるために、世界が
存在しているような
そんな、歌う宝石のかけら と
なること
(後略)
この美しい言葉の歌は、メロディもわからないのに
せせらぎのような、木々の梢を吹き渡る風のような調べをもつ歌として
こころの奥底に刻まれる。
そして、この歌を刻んだこころに季節がかけぬけ
日々が積み重なっていく。
物語のチエーロたちは、迷いながらいまを生きるわたしたちであり
作者からこの歌を贈られたのも、チエーロたちであり、わたしたちなのだと思う。
読み終えたあと
栞は最後のページにはさまれたままになるだろうが、
この歌はわたしのこころにあり、人生の灯となって響きつづける。 |
|
|
 |
 |
 |
|