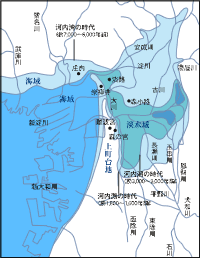 |
 古代の大阪の地形は現在とは大きく異なる。縄文中期、広大な河内湾に上町台地が半島のように突き出ていた。その後、河内潟、河内湖と変貌していくなかで、大阪平野が形成されていった。『続大阪平野発達史』(梶山彦太郎・市原実)より 古代の大阪の地形は現在とは大きく異なる。縄文中期、広大な河内湾に上町台地が半島のように突き出ていた。その後、河内潟、河内湖と変貌していくなかで、大阪平野が形成されていった。『続大阪平野発達史』(梶山彦太郎・市原実)より |

上町台地の北端、都心の中に緑が広がる難波宮史跡公園の大極殿跡に立つ。大阪城天守閣に臨み、遠くたなびく雲の下には二上山、その背景には飛鳥が控え、手前には古市古墳群がある。晴天の日には古代から近世までの歴史のパノラマが見渡せる。目の前には、大阪歴史博物館も建つ。街の中心、上町台地は歴史の宝庫でもある。緑豊かな風景といっしょに、悠久の歴史の軌跡を訪ねてみたい。
まずは難波宮の歴史をひもといておこう。予備知識を仕入れておくと、歩いた時の楽しみが倍になる。
都が飛鳥から難波長柄豊碕宮に遷されたのは、皇極四年(六四五)の大化の改新がきっかけだ。当時の日本は国際的な緊張関係の中にあり、難波の地は難波津という海の玄関を抱え、外に向って開かれた都を置くには最適の地だった。難波宮には、中国、朝鮮との外交を司る大郡、使節の迎賓館である難波館などが置かれ、外交の要所としての機能を果たしたのである。
宮地の造成の後、新宮の建築が白雉元年(六五〇)に始まり、白雉三年に完成する。『日本書紀』には、その宮殿を「殫く論ずべからず」(言葉に尽くし難いほど立派であった)と記されている。これがいわゆる前期難波宮で、孝徳天皇の死後、都が飛鳥や近江に移ってからも副都として重要な役割を果たす。朱鳥元年(六八六)、天武天皇の時代に失火により全焼するが、神亀三年(七二六)には聖武天皇の命で再建がはじまり、天平四年(七三二)に建設は一段落。これが後期難波宮で、天平十六年(七四四)には皇都と定められたが、延暦三年(七八四)にその歴史を閉じる。
難波宮が孝徳朝から百五十年間もの長きにわたって存続したのは、この地が政治、外交、軍事、経済、交通の要衝であったことを物語っている。飛鳥時代の前期難波宮、奈良時代の後期難波宮は、位置がほぼ重なり、近世には大坂城の城下の中にあった。難波宮跡公園は上町台地の歴史の層を実感できる絶好の散策ポイントだ。
 |
| 発掘中の後期難波宮朝堂院南門跡(手前)から大極殿基壇、大阪歴史博物館を臨む(大阪市文化財協会提供) |
一帯は、難波宮の官庁街にあたる場所である。広々とした敷地の中に、前期難波宮の朝堂院跡の大半と、後期難波宮の大極殿・朝堂院跡のほぼ全体が収まっている。今、そこには大極殿の基壇が再現されて横たわる。かつて、基壇の上には礎石が据えられ、柱には瓦葺の屋根があった。九間×四間(三十五・二×十四・六メートル)の当時としては巨大な建築である。その周りは回廊がめぐらされ、内庭部は玉石敷だったという。大阪歴史博物館で原寸大に復元された大極殿を見た人は、貴族や役人が参集し厳かな儀式がとり行われた往時の栄華が浮かぶことだろう。
|