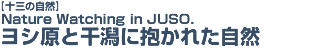
川面にはねる魚、羽を休める渡り鳥、干潟に遊ぶシオマネキ。
十三で見つけた自然のゆりかご。
阪急十三駅東口から歩いて五分、十三大橋のたもとの土手に立つと、淀川の静かな流れが目の前に横たわる。対岸には梅田スカイビル、MBS放送など、都心にそびえる高層ビル。阪急電車が渡る上流へ少し行き、土手を降りると十三干潟だ。長く伸びたヨシ原とくっつきながら、下流側に広がっている。この辺りは海水と淡水が混ざり合う汽水域。多様な魚類、貝類、甲殻類が生息し、それをエサにしている鳥もたくさんやってくる。
「干潟で観察できる野鳥の種類は百二十六種類。日本の野鳥のおよそ四分の一の種類が、ここで生息を確認されています」
淀川ネイチャークラブ会長の小竹武さんの説明によると、秋から冬にかけて、干潟の周辺は、数千羽のカモ類が羽を休める。ユリカモメやハマシギの群れもやって来る。
干潟の苔に被われた泥土をじっと見る。無数に開いた小さな穴から、やがてシオマネキが顔を出す。近づこうとすると、いちはやく人影を察して穴に引っ込む。
ヨシ原の茂みは鳥が巣をつくり、魚が産卵をする自然のゆりかご。緩やかな川の流れが育んだ干潟とともに、淀川の生き物たちにとって、なくてはならない棲家であり休息地だ。一見、水と緑と泥以外は何もないような空間が、実は生き物たちの楽園だった。
 |
淀川ネイチャークラブは、古くから「ふれあい教育」などさまざまな町づくり活動に取り組んできた小竹さんを中心に、平成二年に発足。毎月第四日曜の午前九時三十分から、十三の河川敷に集まって、自然観察を続けてきた。取材当日も、朝から陽射しが強かったにもかかわらず、望遠鏡を抱えてたくさんのメンバーが参加。親子連れも加わり、午前中の時間、野鳥の姿を追った。この日、観察できたのは、ダイサギ、ササゴイ、セッカなど。望遠鏡の視界に現れた、魚を探して干潟を歩くササゴイの黄色いクチバシが一段と鮮やかだった。
「朝、太陽が昇るころは、川面に伸びる日の光がきれいですよ」
小竹さんはしばしば早朝五時前にこの辺を散歩し、風景を楽しむ。
クラブのメンバーで川沿いのマンションに住む久保田明さんも、ここの風景が大好きだ。
「自然観察会も好きですが、私の部屋からの眺めもいいですよ。渡り鳥がやって来る季節には、お昼ご飯を食べる時も、わざわざ窓辺に椅子を持ってくる。ビールを飲んだりもします。雪見酒ならぬ鳥見酒です」
写真スタジオを経営するカメラマンの菊井睦夫さんも野鳥に魅せられた一人。鳥の写真を撮り続けている。「魚はね、満ち潮に乗って泳いでくるんです。鳥は魚の通り道をよく知っていて、ちゃんと待っている。見ていると面白いですよ。こんなにたくさんの鳥が棲家にしている淀川を、なんとか守ってやりたいですね」
現実には、ヨシ原と干潟の近くをモーターボートが走り、土手の下の川辺がモトクロスで荒らされるという問題が起きている。生き物たちにも悪影響が出ているというのだが、なかなか規制ができないという。淀川ネイチャークラブでは、ヨシ原、干潟を含む淀川汽水域を国定自然公園指定してもらおうと活動を始めた。
声高に自然保護を訴えるのではない。楽しみながら、ぼちぼち続けるのが活動の秘訣なのかもしれない。
 |
十三 十三 淀川育ち
潮の満ち引き 街の燈流れ
川面きらりと ぼら はねて
しじみ ざりがに 満月照し
芦の茂に 鴨宿る
小竹さん作詞の「淀川育ち」の一節だ。歌にも、淀川の流れのようなゆったりとした愛情が感じられるではないか。
この日も水の下で、ぼらが何度もはねていた。
十月には、シギの第一陣が干潟にやってくる。渡り鳥の季節はもうすぐだ。
●淀川ネイチャークラブ定例観察会の問い合わせは
大阪市淀川区宮原4-2-105 コーヨーカメラ
TEL.06-308-2704
|