 |
浪花百景 あみだ池
(大阪歴史博物館蔵) |
この堀江もまた、西船場同様、新開地でした。しかも堀江の開発は西船場より遅かったんです。元禄十一(一六九八)年、区域を南北に分ける堀割が通ってから、堀江の開発は本格化したんです。その活性化を狙うて建てられたんが、和光寺です。「阿弥陀池」いうたほうが通りがよろしいやろか。元禄五(一六九二)年に新寺の建立を禁止した幕府が、わざわざ用地を与えての建立です。阿弥陀池は、信州善光寺本尊阿弥陀如来の出現地とされ、住職も善光寺の住職さんが兼務した、いいます。境内は遊興的な要素も強うて、芝居や見世物興行が許可され、楊弓場などもありました。植木市も開かれてました。当時としては一大娯楽センターやったんです。各地からの寺社の出開帳もよう行われました。池の中央に立つ宝塔は、今も昔も阿弥陀池のシンボルですな。
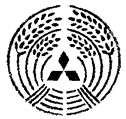 |
| 土佐稲荷神紋(「土佐稲荷神社略記」より)中央に三菱のマークが入っている。 |
西船場と違うて、堀江にはほとんど蔵屋敷はありませんでした。唯一あったのは、土佐藩のそれです。他の蔵屋敷が昔をしのぶよすがをほとんど失ってしまったのに対して、ここには屋敷の鎮守、稲荷社が残っています。「土佐公園」の一角に残る「土佐稲荷社」がそれです。境内を囲む玉垣には「三菱銀行」「三菱商事」など三菱グループ系企業名が目立ちます。それもそのはず、三菱は土佐藩の藩営事業土佐商会を継承した会社で、明治七(一八七四)年東京に移るまでこの地を本拠としてたんです。創業者岩崎弥太郎が自己の三階菱の家紋と、土佐藩主山内氏の三柏紋を組み合わせて、現在に至る三菱マークを定めたのもここやったいいます。ここは三菱グループ発祥の地なんです。よう見ると、土佐稲荷の神紋の真ん中にも三菱のマークが入ってまっせ!
堀江で忘れたらあかんのは、「橘通り」です。家具、建具、仏具などを扱う店が集中する、堀江で一番賑やかな通りでしょう。これは主に明治以降、ここに家具、建具、仏具その他の道具類を扱う業者が集中した結果です。最近ではその東寄りには若者向けの店が続々オープンし、今やアメ村、南船場と肩を並べんとする勢いの、熱いスポットとなりつつあります。
西船場も堀江も、上町や船場に比べたら、新開地です。せやけど、これほどいろんな要素を含み込んだ地域も、江戸時代の大阪には、他にはあらへんかったでしょう。明治維新期には、木津川を挟んだ対岸の川口に、外国人の居留地ができます。また、江之子島には西洋的な外観の大阪府庁が現れます。けっこう、最初に文明開化の息吹に触れたんは、船場や上町よりも、西船場やったかもしれませんな。 |