 |
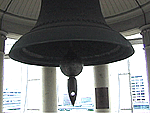 |
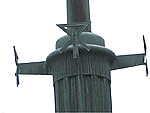 |
||
| 現在、鐘を収容している塔は旧庁舎の塔を復元したもの。屋根に市章「みおつくし」のマークが飾られている。 | 鐘は富山県高岡市の老子製作所で製作された。口径は「よ・い・こ」にちなんで4尺1寸5分(約1.26m)で作られている。 | 「みおつくし」(澪標)とは昔、難波江の浅瀬に立てられていた水路の標識のこと。天保年間の絵図には現在の市章と同じ形の杭が描かれている。大阪の繁栄は出船入船に負うところが多く、人々に親しまれ港にゆかりの深い「みおつくし」が明治27年4月、大阪市の市章として制定された。 | ||
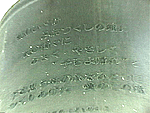 |
 |
|||
| 鐘に刻まれている銘文 「鳴りひびけ みおつくしの鐘よ/夜の街々に あまくやさしく“子らよ帰れ”と/子を思う母の心をひとつに/つくりあげた愛のこの鐘/昭和30年こどもの日に 大阪市婦人団体協議会」(大阪市婦人団体協議会は、現在、大阪市地域女性団体協議会に名称を変更しています) | 母子像と手をつなぐ子どものレリーフ。しっかりと子どもを抱きかかえて育てるように、子どもたちが手をつなぎ「みおつくしの鐘」の意志を継いでいくように、との思いが込められている。また母子像は今日の地域女性団体のシンボルマークにもなっている。 | |||