|
『邯鄲』あらすじと舞台経過(写真は当日の舞台より)
昔むかしの中国のお話です。
ここは、古い都のあった邯鄲の里。
ある時、この里に泊まった旅人が、宿のお礼にと、枕を置いて行きました。
それは、ほんのひと時まどろむ間に来し方行く末(=過去未来)の悟りを開くという、世にも不思議な<邯鄲の枕>だったのです。
◆ ◆ ◆
蜀(しょく)の国の青年、盧生(ろせい=シテ)は、モヤモヤとした底知れない悩みを抱えて旅をしていました。
野を越え山を越え、来る日も来る日も、ただひたすら歩きつづけました。
そうして、邯鄲の里にたどり着いた盧生は、ここで宿を取ることにします。
「お一人旅のようですが、どのようなわけなのですか」と、宿の女主(=アイ)が尋ねると、盧生は「楚(そ)の国の羊飛山(ようひさん)に尊い僧がいると聞き、人生について大事な教えを乞いに」と答えます。
女主はそれを聞き、<邯鄲の枕>で寝てみるように勧め、「その間に粟のご飯でも炊いておきましょう」と言うので、盧生は、さっそく床に横になってまどろみます。
外はまだ日が高く、乾いた大地に降るにわか雨の音…。
すると、枕元で声がして、盧生は起き上がります。
皇帝の勅使(=ワキ)がやって来て、なんと、「楚国の帝位を盧生に譲る」と言うのです。
盧生は玉の輿に乗せられて宮殿へ向かいます。
◆ ◆ ◆
さて、雲の上人(くものうえびと=貴人、皇族)となった盧生が、玉座から眺めたありさまは、立ち並ぶ宮殿には光が満ち、金銀の砂が敷かれ、四方の門には宝石がちりばめられています。
 |
| 盧生の栄耀栄華はこのうえなく、その絢爛たる宮殿の様子が描写されます。 |
出入りをする人々の衣装までもが光り輝いて、仏様の住む常寂光土(じょうじゃっこうど)の都や帝釈天(たいしゃくてん)の居城もかくやと思うほどの美しさです。
幾千万もの貢ぎ物を献上する諸侯が行列を連ね、その旗の流れは天を彩り、はためく音は地に鳴り響いています。
永遠の時を願う詩にあやかって、東には、三十余丈の高さに銀(しろがね)の山を築いて金の日輪(にちりん)を飾らせ、西には金(こがね)の山を築いて銀の月輪(がちりん)を飾らせるという壮大華麗な庭…。
やがて、五十年の歳月が過ぎ、大臣たち(=ワキツレ)が、千年の寿命を保つという仙界の酒を持って参上し、盧生の治世を寿ぎます。
 |
| 帝位に即いて五十年が過ぎ、一千歳まで寿命を保てるという仙薬の酒が献上されます。舞童の役は味方葵(あおい)ちゃん。 |
祝宴では、舞童(=子方)が繁栄を称えて舞い、盧生も、絶頂を迎えた栄耀栄華を歓んで、自ら舞(=〔楽〕がく)を舞うのでした。
 |
 |
| 尽きることなき楽しみの中で、盧生も自ら立って舞います。 |
『邯鄲』の見どころの一つ、〔楽(がく)〕。一畳の四方を柱に囲まれた中での舞をいかにゆったりと見せるか。狭い空間を雄大な宮殿に見立てた、能ならではの発想。 |
そのうちに、盧生は月世界の住人となり、昼かと思えば夜、夜かと思えば昼、四季折々の風景が一度に目の前に広がり、春夏秋冬のすべての花が一斉に開くという、この世のものとは思えぬ素晴らしさを味わいます。
 |
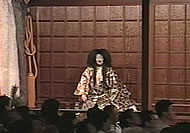 |
| 舞を舞う盧生はいつしか天上の月に同化してゆきます。 |
遥か天空から、まるで宇宙さえも手中にしたかのような盧生。 |
かくして時は過ぎ、五十年の栄華も終わり、宮殿も宝物も大臣たちの姿も次々と消えてしまいます。
 |
 |
 |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時は過ぎ、数多の人々も宮殿楼閣も財宝も消え失せて…。
五十年の栄華が夢の中の出来事であったことを表現する能のダイナミズム。
宮殿だった一畳台は再び宿の寝台に。
飛び上がった空中で、横になった形になる「飛び込み」の型に挑戦して見事に決まった様子をVTRからピックアップした連続写真でお楽しみください。 |
…と、「粟のご飯が炊けましたよ」と告げる声がして、盧生は目を覚まします。
 |
| 宿の女主が盧生を起しにきて、粟飯が炊けたことを告げる。 |
しばし茫然としたあと、盧生は、「百年の歓楽を尽くすと言ったところで、それも命が終われば夢と同じこと。五十年の栄華を夢に見ることが出来たのだから、私にとって、これ以上望むことなどないではないか。それにしても、今までのことは、ただ<一炊の夢(いっすいのゆめ)>だったのだなあ」…<邯鄲の枕>こそ、求めていた人生の師であったのだと枕を礼拝し、望みを叶えて故郷に帰ったのでした。
花形能舞台
第三夜 7月22日(火)19:00開演(開場18:30)
お話 石淵文榮
能『邯鄲』noh KANTAN
シテ:盧生 味方 玄
子方:舞童 味方 葵
ワキ:勅使 福王和幸
ワキツレ:大臣 福王知登
山本順三
輿舁 是川正彦
中村宜成
アイ;宿の女主 善竹隆平
笛 竹市 学
小鼓 成田達志
大鼓 山本哲也
太鼓 前川光範
後見 上野雄三
赤松禎英
地謡 片山清司
浦田保浩
河村晴道
浦田保親
吉井基晴
梅若基 |
|