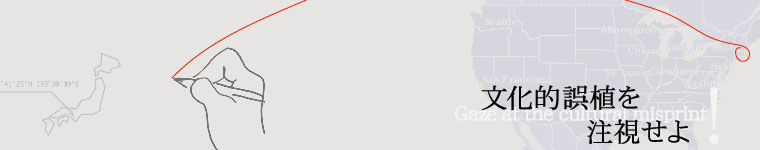| ボストンのMITに滞在しながら現代美術シーンを紹介します。 |
|
|
text
+ 池田孔介
 |
1980年生まれ、美術家。東京藝術大学大学院修了。現在、文化庁在外研修員としてボストンのMITに滞在中。 WEB SITE
|
|
|
|
|
ジャン=リュック・ゴダール『はなればなれに』の中のワンシーン。騒々しいカフェにいる三人が「一分間黙っていよう」と言い合わせ、その間映画の一切の音、室内の音楽や周囲の雑音を含め、すべての音がしばし、消え失せてしまう。しかし、そんなことをせずとも私たち賢明な観者は、彼らの一分間の沈黙を感知するのは可能なはずです、つまり、騒々しくレコードが鳴り、周囲はおしゃべりを続ける、そのなかで中央の三人が黙ってさえいれば、観者はその「沈黙」をそれとして認識可能でしょう、たとえ映画自体からは様々な音が発せられていたとしても。私たちはここで、映画それ自体の音を沈黙として感知しているのではなく、スクリーン内に映し出された映像の意味を正確に読み解き、実に正しくそこから「沈黙なるもの」を認識しているのです。ここにおいて観者は、「今、この劇場で聴いている音」と「映画の中で示されている音(のなさ)」という二つの階層を識別し、このシーンが「沈黙する三人」を意味するということを読み解くことができ、つまるところ私たちの認識はここで、実際に劇場の中で音が放たれているか否かを問題にしていないのです。だとしたらなぜゴダールはわざわざ、映画内の一切の音を断ち切るような暴挙に出る必要があるのでしょうか。
|

| | |
ジャン=リュック・ゴダール「はなればなれに」(1964)
|
それはひとまず置いておいて、今回はやや趣向を変え、私の元に届けられた雑誌『新潮』二月号から二つの小説、青木淳悟「いい子は家で」と福永信「寸劇・明日へのシナリオ」を取り上げることにしましょう。日本からはるばる届いた文芸雑誌を開き、この誌上に並んで配置されている二つの小説を読んでみると、何か拭いきれない違和感のようなものが頭の中に残ります。その感覚を紐解くべく注意深くこれらを読み比べてみれば、まずは一つのことに気づかされるでしょう。細部から全体の構造に至るまで実に様々な点において見られる、なんとも奇妙な一致。両者とも舞台が現在の日本で、家族を主に扱っていることは一見して明らかですが、青木淳悟の一二〇枚にわたる小説の後ろにぺたりと貼り付くように福永信の小説が存在していることからして、この二つの小説の繋がりは読む者の関心を引かざるを得ません。
まずは細部、「門限はないはずなのに夜の外出は極端に嫌がられる。」(青木)に対し「門限の設定こそ明文化されていなかったが、そこは親、遅い帰宅は心配し、理由がなければ、これは容赦なく叱責した。」(福永)。「目標物となる国道沿いの大型店(筆者注:後にこれがショッピングセンターである事が示される)」(青木)に対し「国道沿いになかなか充実した品揃えのホームセンターがあり」(福永)。奇妙な一致はより大きな小説の構造にも及びます。一、主人公と兄弟、その両親、さらにもう一人の他人という人物構成。二、主人公とその家族が住んでいる一軒家、もう一人の他人が住んでいるマンション/アパートという配置関係。三、主人公が家から出て他者のマンション/アパートへ行き、そこで起こる出来事が各々の小説のちょうど中央に据えられている。四、父の死(しかも両者とも、死んだ当人は自分の死さえも気づかず「死んで」いる)。
このような不自然なまでの一致は、しかし、この二つの小説の差異をも強調することになるでしょう。例えばそれはそれぞれの情景描写の方法に見て取ることができるでしょうか。
「林道にでもまぎれ込んだような、感じのいい舗装道がつづいている。その住宅のない雰囲気と薮や空き地や森の多さに驚いた。宅地と畑だらけだと思っていた地元にもまだこんなところがあった、という発見だった。」(青木)
「湿った足跡が土の上にくっきりとついていた。玄関へと続くコンクリートの通路にも残されていたが、外へ出る前に、不意に消えていた。それを見た何人も、両脇を抱えられ、足をジタバタさせている男の子を想像したものだった。」(福永)
前者の情景描写が、その指示対象を見る主体たる主人公の「驚き」という感情に回収され、読者はこの描写を通じ主人公の感情の喚起を理解することができるでしょう。他方、後者の描写はいかがなものでしょうか。それは読者をどこへも連れて行かない、単にそれがそれとしてあるのみとでも言えば足りるでしょう。あえていえば前半部分「湿った足跡が土の上にくっきりとついていた。玄関へと続くコンクリートの通路にも残されていたが、外へ出る前に、不意に消えていた。」からは何か「謎めいた雰囲気」なるものを読み取ることは可能ですが、しかし、「それを見た何人も、両脇を抱えられ、足をジタバタさせている男の子を想像したものだった」というセンテンスとの接続によって再び、そのような寓意性は消え去ってしまう、つまり、引用前半部において生み出されうる情景の意味が読者の意識の中に結像するその瞬間に、すぐさまその意味は失われてしまうのです。この福永信によってもたらされた情景描写から私たちが何らかの含意を読み取ることはほぼ不可能であり、ここに、青木淳悟の小説との大きな差異が見て取れるでしょう。
次に青木淳悟の小説における二つの世界の存在、世界の二重構造ともいうべき特徴に注目しましょう。このような性質は端的に以下の場面に現れています。母親や兄との日常的な場面がしばし展開された後、主人公孝裕は三連休をガールフレンドのマンションで過ごす。彼女の帰りを待つ間、部屋にあるバターをいじりながら彼は「土下座するように両手をついて床の上のバターに顔を寄せる。においを嗅ぎ、表面を下で舐め、それからにむり、にむり、噛んで食べ」る。しばらくして座りなおすと「首元で鈴が鳴るのである。本物の鈴が鳴った。鈴のついた革製の首輪だった」。このシーンで、ほとんど明示的に「ある動物」へと変化しているのですが、その後再び、孝裕は人間へと戻ります。このバターをめぐる「変化」のシーン周辺で、主人公は「孝裕」という固有名から「彼」という代名詞へとその指示記号を変えられていることは注目に値します。固有名を失った主人公は現実とは異なった、しかし全くもってそこから切り離されているというわけでもない世界に出会う。そしてその後も何度か孝裕はそのような世界に遭遇し、そしてまた現実へと戻ってくるのです。
そのような、あからさまに言って「幻想的」な世界観の構築は主にドラッグを用いた様々な表現形式の中に散見することができるのですが、この作品がそれらと袂を分つのは、そのような「幻想」シーンを支える土台が極めて日常的、ドラッグなどとは遠く離れた舞台である、ということでしょう。さらにいえば、この「幻想」シーンは、次のような「日常」世界における記述によって善くも悪くもしっかりと支えられています、「イマジネーションが豊というのか、ただ空想癖が強いだけか、彼はたまに目に見えないものをみてしまう」。すべての「幻想」シーンは、結局のところ、この一文の中に回収され、「日常」という平面の上に据えられる。いかなる「幻想」も、その土台を揺るがすことは決してない。言い換えれば、彼は何度となく「こうであるかもしれなかった」世界を日常の中から発見するでしょう、しかしそれは同時に「にもかかわらず、こうでしかない」現実、その被限定性を強化するかのように働きます。
このような被限定性をもち存在する日常世界のありようは、柄谷行人がクリプキを通じて見てとる「現実性」、「こうであるかもしれなかった」という可能世界を通じ、にもかかわらず「こうでしかない」という単独性をもつ現実、クリプキ的現実の議論と繋がるものです。「村上春樹の『風景』」(『終焉をめぐって』所収)において柄谷行人は、村上春樹の小説中に固有名や具体的な数字が散見されることを指摘し、それらの無意味性は先のような単独的現実を拒否するものとして機能しているとします。「バルザックの小説に出てくるカワウソ」「クロード・ルルーシュの映画でよく降っている雨」(『1973年のピンボール』)「彼女の死を知らされた時、僕は6922本目の煙草を吸っていた。」(『風の声を聴け』)等々。具体的な名前や数字というものは通常、その固有性、唯一性ゆえに、ある歴史的な出来事、小説と現実世界とを結ぶ交換不可能な要素としての役割を果たしうると考えられます。しかし、上の引用に見られるような固有名・数字はほとんど何をも意味しない、むしろそれは積極的に無意味であることによって歴史的な年号や固有名を無効化し、世界を任意な記号の舞台へと導く。それは「こうでもあるし、こうでもありうる」という恣意性の舞台なのであり、それを支えるのが村上春樹の小説に登場する固有名や数字の効果だと考えられるのです。
同様に、福永信の小説にも様々な数字が登場します。「第五場」における数字の現れを、その順序通りにあげてゆけば、主人公の父親が「四度目をなかなかノックすることができず」、「軽く三回たたいたが」娘からの応答はなく、「妻は大型の本を二冊抱えて」現れ、「一歩下がって一冊を差し出」す。このようなカウントダウン式(!)に配された五から一までの数字が読者にとって何の意味も形成しないのは明らか、それは物語に付加的な意味を与えるというよりも、むしろ物語の「物語」たる構造を阻害しているようにさえ思えるのです。あるいは『群像』2004年9月号に掲載された『五郎の読み聞かせの会』における、何度も過ぎ去る「五分」、蚊が「五郎」の腕で血を吸う「五秒」、「五年」振りの対面、「五郎」のために焼かれる「五枚」のパン(この小説に関しては、 こちら の拙文を参照されたい)、これらのシークエンスにも等しい効果を見て取ることができるでしょう。ここでの数字は、その無意味性において村上春樹における数字と一見類似しているように思えるかもしれません、しかし柄谷行人によるところの「私的であり無意味」な村上春樹における数字が、そもそも意味があるものの無効化の水準において機能しているのに対し、福永信が用いる数字は元より何の意味もない。単にそれは小説がある物語として展開して行く時間的・水平的な流れを阻害するもの、それこそ読むことに対する障害物のように機能しているのです。いわばそれは村上春樹的な無意味(non-sense)ではなく、反意味(anti-sense)の次元において紡がれていると考えるべきではないでしょうか。小説が何らかの物語をもち読者がそこへと没頭してゆく構造をことごとく垂直的に切断してしまう異物性を孕んだ数字。
それに加えここでの議論を支える要素として、福永信の小説内に現れる数多くの括弧、しかも語の強調のための「」でなく、語義を副次的に示すための()の存在に触れる必要があります。例えば第一パラグラフにあたる「第一場」のほんの数行の中に三度、括弧が登場しています。「ここ(アパートの一室)を退出してほしい」「白河家(一戸建、築十五年)は無人だった」「ここ(白河家)に、」など、率直に言ってうっとうしいほどの数の()がほんの数行のうちに散りばめられており、しかもそこに含まれる情報は、小説の進行に対して補助的な効果を持っているとは到底思えないのです。もはや言うまでもなくこれは先ほど指摘した反意味としての数字とほぼ同じ役割を持ち、小説の水平的展開を阻害する。
もう一点、これまで私はそれに全く気づかない振りをして論じてきたのですが、この小説には実に奇妙な仕掛けがあります。通常、この手の文芸誌は二段組みという形態をとっており、読者は一段目の行を読み終えた後、一段目の次の行へ、それ終えるとまた次へという反復運動を何も意識しないままに行います。しかしこの小説の場合、一段目の一行を終え、そのままそこにある空白を飛ばして同行の二段目へと進み、二段目の同行を読み終え、次の行の一段目へという具合なのです。つまり一段目と二段目との間にある空白は、おおよそ無意味、というよりも円滑な読書を阻害するようなもの、すなわち先述した数字や()と同様の効果を持つものとして、読者の行為へ作用します。先ほど物語的展開を水平的、それを遮断する数字を垂直的と述べましたが、ここの空白もそのような構造と重ねて捉える事ができるようです。つまり、読者が上から下へと文字を読み進めてゆく、その垂直軸の反復運動は水平に配された空白によって切断され、読む行為は絶えず躓かされる。それにより読者は、いま、ここで、読んでいる、というその意識を強いられ続けることとなるのです。
|

| | |
そうして私たちは、福永信の小説から「何か」を感じ取ることなく、それを読み終えることとなるでしょう。現代の家族像?今日的コミュニケーション不全?確かに、そのような主題を感じさせる部分は散在しているかもしれません、これらの断片は、しかし、その含意を読者に伝える手前で、様々な阻害物によってその意味を失ってしまう。そもそも小説から「何か」を感じるとはどういうことなのでしょうか。いみじくも私たちは青木淳悟の小説から、先に挙げたような主題、「現代の家族像」なるものを感じ取ることができるでしょうし、またそのように論じられることもあるでしょう。ですが、ここにおいて読者はもはや読者(reader)であるのでなく解者(understander)となっていることを指摘しておかなければなりません。私たちは小説を通じて様々な「世界観」や「雰囲気」なるものを解することとなりますが、それはここで為されている読む行為を忘れ去ってこそ獲得できるものなのです。しかし福永信は読者にこれを許さない。彼の小説は、読者を読者でしかない者へと留め、小説を小説それ自体でしかないものへと留めます。
福永信は小説の可能性をギリギリまで絞り、その存在がかろうじて成立するであろう「読まれる」という地点まで、その広がりを囲い込んでゆきます。このような「限定性」と、先に見てとった青木氏における「現実の被限定性」とを区別しておく必要があるかもしれません。あくまでも後者の小説が「物語」の水準において日常の被限定性を表象するのに対し、前者のそれは「物語」そのものの成立を拒否し、小説が小説として存在する条件に限定性の枷を付してゆく。そのような限定性が、いかにも「貧しい」限定であることは否定しません、しかし同時に、それはこの上なくラディカルな限定/還元であることをも確かに感じることが出来るのです。ここで私が取り上げたいくつかの点は、あらゆる意味で「小説」的な実験とは到底言い得ないかもしれない、しかしそれが何の問題だというのでしょう。小説的であり得ない、にもかかわらず小説そのものでしかない、ここにおいて読者は言いようのないフラストレーションを感じることとなる、いや、これは最大限の賛辞です。
ここで私たちは再びゴダールのあの「沈黙」へと目を向けることになります。「一分間黙っていよう」という言葉とともに、映画の中の一切の音がしばし消え失せる、あの沈黙は実際、何の解釈も要請しません、単に「沈黙」を文字通りの「沈黙」として観者の前に放り出してみせるのみです。しかし、画面の意味を解釈することに慣れている観者にとってこのような沈黙はいかにも不自然、ここで感じる違和感と福永信が提示する違和感とは、ほぼ同様の効果を持ち得ているようです。映画的シークエンスを無骨に切断するような沈黙と小説的展開に障害物を加えてゆく要素たち。雑誌の表面に刻印された文字群へと向けられた私たちの意識はやがて、そこにある一つの空白を発見することとなる。『新潮』すべてのページの中央を水平に貫く長い長い空白、空白は空白として言いようもなく立ち現れる。私たちはその存在を忘れ去るところから読書を始めていた。
|
|
|

|