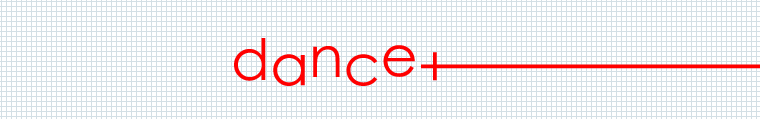
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
28 京都の暑い夏2007ドキュメント Vol.3
ビデオサロンレポート(2)映画とダンス
by 森本万紀子 [dance+]
今年のビデオサロンは、1日目と2日目に共通したセレクションの切り口として“コミュニケーション”を据えました。踊るひと、つくるひと、観るひと。さまざまな関わり方でダンスの周辺をうろうろしているひとたちと一緒に、映像を観るという行為を通してコミュニケートできれば、という願いも込めた企画です。
【古今東西のダンス】のセレクションを受け持ったのは、自他ともに認めるdance+のエンタメ担当者。「コミュニケーション」というテーマを気ままに広く捉えて我が家のビデオ棚をひっくり返してみれば、さまざまなコミュニケーションのかたちが見えてきました。
例えば、振付家とダンサーのコミュニケーションがよく見えるものとして取り上げたのは、ウィリアム・フォーサイスとフランクフルト・バレエ団による『インプレッシング・ザ・ツァー』のメイキングビデオと、講師イニャーキ・アズピラーガが持参してくれたヴィム・ヴァンデケイビュスとウルティマ・ヴェズの『Bereft of a Blissful Union』のメイキングビデオ。前者は振付家フォーサイスがリハーサル中いかに場を盛り上げながら、ダンサーたちとムードを共有していくか(同時に、難解とされるフォーサイス作品のリハーサル風景がこんなにも軽いノリでイケイケなのか!)がよく分かる傑作10分ドキュメンタリーで、何はともあれ上映したかった1本でした。後者は逆に、振付家とダンサーの対立をクロースアップした部分を抜粋。それぞれの主張を激しく言葉でやりとりする様子は、「言われたことをそのままやりがち」と捉えられやすい日本人ダンサーへ向けたイニャーキ自身のおススメ箇所で、びっくりするほど口で負けない、引き下がらない、そして最後まで納得しない(!)ダンサーの姿勢は、新鮮でもありました。
あるいはインプロヴィゼーションにおけるコミュニケーションの一例として、2005年にびわ湖ホールでも上演された『D’avant』より、1人のダンサーをサッカーボールと見立てて、他のダンサーたちがサッカーに興じるシーンの、流麗なコンタクトを取り上げたり、2人の人間が、お互いに寄りかからないと立てないようなバランスを保ちながら歩き続けるトリシャ・ブラウンの『Leaning Duet』を取り上げたりと、ダンスにおけるいろいろな意味での“コミュニケーション”を示唆するようなセレクションを心がけました。
しかし、この日のプログラムの大半を占めたのは、映画からのダンスシーンです。ほぼ全てレンタルビデオ店で借りられる類いの、格別レアでも何でもない映画の中で、物語を語るため、あるいは彩るために挿入されるダンスシーンの数々にスポットライトを当ててみました。
■ 映画の中のダンス① “バトル”におけるコミュニケーション
『TAP』で最も有名な“チャレンジ・シーン”では、サミー・デイヴィス・Jr.を含む老人たちが、若きグレゴリー・ハインズの生意気さを「そいつは俺らに対するチャレンジだな!」と煽動します(実際はただ自分らが踊りたいだけ)。10名ほどのじーさんら全員で輪になって順番に自らの技術を披露していくのですが、輪の中でステップを披露するひと、そのリズムにノリノリで囲むひとたち、そこにあるのはお互いに対するリスペクトだから、耳を澄ませることと、伝えることが成立するわけです。デイヴィスとハインズが向かい合ってステップをつないでいく様子は、ほとんど会話です。
『ユー・ガット・サーヴド』より抜粋した、ヒップホップにおける、いわゆる“バトル”も、要は“喧嘩する代わりにダンスで勝負”するわけなので、輪になって踊るひとたちと似たようなものです。こっちが挑発すれば、相手もそれに乗って挑発し返してくる、その繰り返しは口喧嘩のようなもの。
■ 映画の中のダンス② “踊りのムシ”の伝播
これはいわゆる“ハーメルンの笛吹き”状態ですが、ひとりのひとにつられて、なんだか周りも徐々に踊りだしてしまう、歌いだしてしまう、そんな伝播の法則もあります。『マイケル』で天使役を演じるジョン・トラヴォルタ、『マルクス一番乗り』のハーポ・マルクス、『フェリスはある朝突然に』のマシュー・ブローデリックはみんなその笛吹きと言えます。これらの映画はどれも、この3人の俳優たちのカリスマ性をうまく使ったダンスシーンを取り入れています。彼らの醸し出すリズムが伝わってくると、周りもついつい乗せられて、楽しくなって、ノリノリで踊り始めてしまいます。
そんな伝播系をミニマルな作品にした例として取り上げたのがトリシャ・ブラウン・カンパニーの『Spanish Dance』。間隔をおいて縦に並ぶ10人くらいのダンサーたちは、ひとりが音楽に乗せて腰を振りながらゆるゆると進んできて前のひとにぶつかると、身体の接触している部分からその動きに同調していき、1人が2人、そして3人4人と徐々にいも虫状態になって、腰をふりふり、ゆるゆる進んでいきます。
*ちなみに“踊りのムシ”というのは、山口で活動している“ちくは”というダンスグループのパタン集から拝借した言葉。この例として、赤ん坊が1人泣き始めると、次々にみんな泣き始めるという状況を挙げていました。
■ 映画とダンス③ 2人の間でのコミュニケーション
ハリウッド・ミュージカル映画の全盛期1930〜40年代には、優れたダンサーコンビが現れました。言わずもがなのフレッド・アステア&ジンジャー・ロジャース、そしてちびっこシャーリー・テンプル&ビル・“ボージャングル”・ロビンソンおじいさんや、さらにはニコラス・ブラザーズの掛け合いも見事なまでです。これはもう、「この2人だからこそ」という抜群の相性が、見事な化学反応を生み出す例です。
こうなると、極端を言えば相性のぴったり合う2人が立っているだけでダンスが生まれてしまうので、いわゆる“ダンス”である必要はなくなってきます。そこで取り上げたのは『藍色夏恋』におけるグイ・ルンメイとチェン・ボーリンの無言の喧嘩シーン。2人とも台北の街を歩いていてスカウトされたという、俳優としても全くの素人ですが、身体をまだうまく自分のものとして操ることのできない17歳という年齢が引き起こす、奇跡みたいな無言のコミュニケーションを目の当たりにします。
■ 映画とダンス④ 素人ダンス
素人ダンスの素敵なところは、身体と運動というものに対して無自覚だからこそ、無防備に“出てきちゃう”何かが存在すること。その、なんだかわけのわからないもの、に隠されている驚きに出会ってしまうと、もうたまらなくときめくのは私だけではないはず。このプログラムを担当するにあたって、どうしても上映したかった映画のひとつでもある『Napoleon Dynamite(邦題:バス男)』のジョン・ヘダーのへなちょこダンスを取り上げました。勉強が出来なければスポーツが出来るわけでもない、オタクでもないのに友だちもいないナポレオンが、これまた絶妙に微妙な選曲のジャミロクワイ『Canned Heart』に乗せて送る“生徒会長選挙立候補者応援ダンス(ソロ)”を披露するくだりです。他人とほとんどコミュニケーションがとれない(とらない)ナポレオンですが、彼のダンスは、自分でもよく分かっていないその“なんだかわけのわからないもの”を観客に伝えることに成功して拍手喝采で受け入れられます。
また、ミュージックビデオ界で名を馳せ、近年映画界にも進出している天才(と言ってしまいます)スパイク・ジョーンズによるプロモーション・ビデオ『Praise You』は、まさにそんな素人ダンスの真髄を確信犯としてでっち上げた傑作です。
■ 映画とダンス⑤ ひとの心をつかむミリオン・ヒット
気分やムードを伝え、ひとの心をつかむことに長けているという、営業の基本コミュニケーション能力的なところにおいて、ミリオン・ヒットのプロモーション・ビデオもあなどれません。ミッシー・エリオットのプロモーション・ビデオはどれをとってもダンスがふんだんに盛り込まれていますが、特に『Loose Control』は秀逸で、太くて粗野なビートに乗せた激しいダンスと急激なカットバックは、観ているだけで音楽とダンスの分ちがたいエリアに引き込まれていきます。
ミュージカル映画にしてもそうです。映画が音を獲得した1920年代に爆発的に人気を集めそのキャリアをスタートさせたミュージカル映画は、いずれも観るひとの中に眠るリズムや音楽や踊りのムシを呼び起こすもの。バズビー・バークレーによる『Gold Diggers of 1935』では何百人というダンサーがユニゾンでタップダンスを披露するという大掛かりなシーンがあります。また、こうした往年のミュージカルへのオマージュとしてつくられたウディ・アレンの『世界中がアイ・ラブ・ユー』でも、日本映画界のミュージカルマニアが結集してつくり上げた1960年の和製ミュージカル映画『恋の大冒険』でも、そのスピリットを伝え残すことに成功しています。
さて、いくつか取りこぼしもありますが、上記のようなセレクションを展開してきた本プログラム最後に上映したのは、松山大学ダンス部の2004年の定期公演のフィナーレを飾った作品です。私がここ数年松山大学ダンス部の魅力にとりつかれているのは、彼らが——コンテンポラリー・ダンスを意識してかしないでかは分かりませんが——“ダンスピースをつくる”ということに励んでいる傍ら、部員勧誘や定期公演のプログラムの合間にはウケの良いヒップホップを踊り(それはまた全員の踊りのムシがムズムズと動きだし、はちきれんばかりに輝いているのですが)、また体育会的な“部活”の在り方を崩さず、かつ50人以上もいる部員ひとりひとりの認知とリスペクトの上に立った関係性を保持しているという、その創作姿勢や集団としての在り方が複合的で偏りがないからでもあります。誰もが等身大の自分をそこに置く素地があるグループであるため、彼らのインプロヴィゼーションを見れば、身体の触れないコンタクトがどれだけの信頼関係に基づいて成立しているか、そしてそれぞれがどれだけきちんと自分の場所を見つけているか、そこに各々の人間性が出てきてしまうということがどんなにダンスをダンスたらしめているか、ということを目の当たりにするのです。
今回のビデオサロン【古今東西ダンス編】では、形態としては、コンテンポラリー・ダンスも挟みながらですが映画の中のダンスを中心にお送りしました。それは“ダンス”と言った時に、必然的にアート系とエンターテインメント系の棲み分けが出来てしまっている現状を少しさびしいと感じる、個人的なモチベーションもあります。ダンスは限られた人のものではない、ということをコンテンポラリー・ダンスが教えてくれたように、ダンスは狭義のアートにとどまるものではない、ということを、両方の側面から見てみたかったのかもしれません。
映画評論家の淀川長治さんは、こどもの頃からとにかく“動くもの”が好きで、雨降りの日に車窓を伝い落ちる雨粒を、飽きることなく見ていたということです。『私の舞踊家手帖』という本まで執筆されるほどのダンス好きでもあり、俳優たちの肉体美(例えばアーノルド・シュワルツェネガー)に心からの賞賛と拍手を送り、『サタデーナイトフィーバー』に至っては、日曜洋画劇場の解説で「ジョン・トラボルタの、あの足! 足! 足! 腰! 足!」と熱狂的に語るほどでした。
動くものに魅せられてしまったひとにとっては、俗にいうエンターテインメントもアートも、ダンスも映画もおしなべて同様に愛してしまうのかもしれません。映画の中での優れた演出における逆回しやスローモーションだけで「これぞダンス!」と大騒ぎする私のような人間にはよくわかる感覚なのですが、そういった部分で、もう少し視線を遠くにやって、自分にとってのダンスがどんなものかということを、広義に考える機会になればなあという、小さな願いをこめてこの拙いセレクションを展開させていただきました。
心おどるような、わくわくうきうきするような、なんだか踊りだしたくなるような、惹きつけられてすっぽり取り込まれてしまうような、ダンスが与えてくれるそんな瞬間を様々なアプローチからキュッと捉えたものが、映画の中のダンスには多分に含まれています。ちょっと角度を変えるとものの見え方がガラッと変わるように、踊るひとも、つくるひとも、観るひとも、いろいろなものに“ぼくの/わたしのダンス”を見いだし、それを更新していってほしいなと思います。
こうした「これだってダンスだよビデオサロン」は、近いうちにスポーツ編をと作戦を練っています。乞うご期待。
|
|
|

|