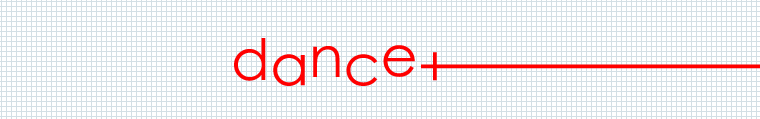
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
|
丹波マンガン記念館のこと
Text:メガネ
「建築的な芸術作品は(…)、あらゆる時代において人類を動かしてきた。打ち捨てられた残骸や廃墟でさえ、我々を魅了する。かたちづくられた空間は、それを知覚する主体との関係に踏み入り、その感情や身体意識に作用せずにはおかない。」
『空の時間Leerzeit –ベルリン、ユダヤ博物館への道のり-』(Museumspaedagogischer Dienst Berlin 2000)より
芸術作品とならんで文化施設でも、鑑賞者に参加を促す傾向が進んでいるのだろうか。たとえば「体験型」を謳ったミュージアムなどを訪れてみると、建築や空間設営に趣向をこらし、ワークショップなどの関連イベントと併せて、何かしら身体を巻き込んだ経験を鑑賞者に与えようとしている。文字情報に秩序づけられた視覚的な啓蒙装置から、体感を前面に押し出した娯楽装置へと、博物館/美術館は重点をシフトしつつあるかのようだ。でもそこで人は、単に知的好奇心を満たし、束の間の非日常的な知覚を得るだけなんだろうか?
いきなり固い話で恐縮だが、博物館/美術館は本来的に、文化財とともに共同体の歴史や価値観を提示し、それらを国民や市民に定着させる役割を担っている。近代になって個人のビジョンを具現化する作品が持ち込まれるようになると、伝統的なものの捉え方や見方は多様な視点で相対化されたり活性化されたりして、新しく生まれた認識を社会に還元してゆくという役割がそこに加わる。つまりミュージアムは、理念上はさておき、いろんな価値の係争の場でもあるのだ。そこで展開される力関係の当事者は、アーティストと鑑賞者だけではない。社会的な利害に分節される集団とか個人とか、あるいは視覚と触覚なんてものの間にも、様々なポリティクスがひらけている。ミュージアムに脚を運ぶっていうことは、美とか教養とか特定の目的に動機づけられてのことであっても、そういった価値を担う諸々の関係の場に、とりもなおさず身をおいてみることなんじゃないだろうか。
同じことは、劇場という文化装置で営まれる舞台芸術にも言えるし、dance+がトラッキングするダンスでは、このところかなり面白い動きが見られたのだけれど、今回は身体と思考に思わぬ地殻変動を起こした、とある記念館の体験を振り返ってみたい。
◆ 丹波マンガン記念館を知っていますか?
京都の市街地から車で小一時間北の山系を越えたところに、知る人ぞ知る小さな記念館がある。この一帯には、明治期から1983年頃にかけて日本の製鉄産業を支えた日本最大級のマンガン鉱脈が広がっており、その丹波マンガンの全体像を後世に伝えるため、1991年に建てられた丹波マンガン記念館だ。創立したのは元鉱夫で初代館長の故李貞鎬さん。安価なマンガンの輸入により廃業を余儀なくされた後、塵肺を抱えながら家族を指揮して同館を設立した経緯と心意気は『ワシらは鉱山(やま)で生きてきた——丹波マンガン記念館の精神史』(発行・同館、編集・虫賀宗博、1992年)に詳しい。
美術に関心のある方なら、2003年の京都ビエンナーレで高嶺格が『在日の恋人』を滞在制作した「穴ぐら」として、この記念館をご存知かもしれない。当時かなりの話題となったこの作品を、京都芸術センターで催された記録展示で目にしていた筆者も、同館の見学会なるものを知り、飛び入り参加することに。前述の書籍の編集を手がけた虫賀宗博さんが主催する集まりとあって、李貞鎬さんの三男で現館長、李龍植さんからかなり突っ込んだお話もうかがえ、とても充実した内容だった。
◆ マンガンを通して見えてくる歴史と地図
まずは資料館で、展示されているマンガンに触らせてもらったりしつつ(持ち上げたら、重っ!)、嫁いできたオモニが何度も逃げ帰ろうとした思い出などを枕に、ぼちぼちレクチャーが始まる。それはマンガンの鉱物としての性質や産業的役割、一家が記念館を設立した背景ともなる日本の産業史、労働史について集められた、膨大な資料を踏まえたものだった。個人、家族の生活の記憶と、地域や国の産業の歴史をダイナミックに横断する李さんのお話の途上、う〜ん、とうなりたくなるような事実が続々と出てくる。近代化の要となる戦略物資であるマンガンと、強制連行や塵肺や差別をめぐる問題は、意図的に避けようとでもしない限りセットなのだ。当事者の記憶と絡めて語られる “不都合な事実”と、初代館長の「ワシらの肺塚」という言葉に打ちひしがれながら、飯場、そして坑道へ向かった。そこでは、また別の風景が開けることに。
◆ 坑道で目にしたことと感じたこと
杉皮葺きの飯場では、人里離れた炭坑に設けられる寝食の場が丁寧に再現されている。炊事場、食卓、寝床を含めて20畳ほどのスペースで、食事は立って摂り、8畳ほどの板張りに多いときは20人くらい折り重なって寝たと言う。そのイメージに身を竦めていたら、展示マネキンの顔がバタ臭いのは、東洋人風のものだと特注で値がはったから、といった話が続く。外見上はその辺りのミュージアムとあまり変わりないが、実は展示のほとんどは家族の手作りだ。だから、表の牛の模型はオモニの手製だとか、昔は端材だった杉皮を入手しようとしたら高くついたといった制作エピソードに事欠かない。
坑道では、歩いて通れるよう堀り広げられ、H字鋼で補強された見学通路から、四方八方に口を開く採掘坑を見て廻る。薄い層状に延びる日本のマンガン坑では、鉱脈に沿って採掘者一人が這い進める程度の穴を、数百メートルもハンマーとノミで掘ってゆくのだという。木馬(きうま)も通せないような狭い坑道からマンガンを取り出したり、牛車(ベタ)まで運んだりする作業まで、すべて人頼み。覗き込んだ鼻先で暗闇に沈む狭い坑道の傍らに、サザエの貝殻に油を注いだ灯りが展示されている。劣悪極まりない労働環境だ。けれども李さんの説明をじっくり聞いていくと、それらと拮抗して、鉱山で生きる仕事人たちの矜持のようなものも見えてくる。効率よく生活の糧を得、かつ命を落とさないための数々の知恵。たとえば、通路から脇へ延びる坑道の落盤防止装置の木材は、「鉄鋼が国全体で不足していたからだが、きしむ音で危険を知らせてくれる」そうな。あるいは、鉱脈は続くが木材では支えきれないと判断されると、一部を支柱に残して奥の採掘を済ませてから、最後に支柱部分からマンガンを取り出すといった方法。そこで培われた身体感覚というのもすごい。「ふつう女で200、男で300キロ担いでましたよ」と言われ、正直、最初はご冗談をと思った。いくら比重の高いマンガンが嵩張らないとは言え、朝青龍2人分…、まてまて、重量挙げの世界記録は…などと考えていたら、脚の長い背負子で持ち上げては数歩ずつ進むのだという。「でも要は、体の使い方ですわ」と、さらり。
こういった想像をはるかに越える話に、思考停止に陥らず感傷的にもならずついてゆけたのは、李さんの存在に負うところが大きい。かつて採掘者として働いた坑道をその手で整備し、今も一人でメンテナンスを続ける彼は、鉱物世界とそこでの人々の生活、仕事に知悉した媒介者であった。薄暗い坑内の各所で足を停め岩肌に触れては、山全体へ、そして数億年の歴史へと広がる地層を読み解き、それにふさわしく働くための道具や身体の知恵を開示してゆく。かと思えば、坑道が潰れてきて木材のばきばき折れる音が背後に迫るといった、身の毛もよだつ体験を、「インディージョーンズも真っ青」と、笑いながら語る。
◆ 記憶の地殻変動 丹波とベルリン
こんな風に展示は、レクチャーで得られた世界の見取り図を感性的に追体験させるものだったが、同時に体験した者の記憶の層に地殻変動を起こし、別の回路へと導くものでもあった。
実は見学会で印象に残ったことの一つに、小一時間の見学を終えて炭坑から出たとき、は〜っと溜息がもれる開放感とともに体に呼び覚まされた記憶がある。ベルリンに、ヨーロッパにおけるユダヤ人の歴史を記念して、2711個のコンクリート柱を並べた一画があるのだが、一歩足を踏み入れると次第に視界が遮られてじわじわと閉塞感に襲われ、出てきたときに必ずやは〜っとなる。同様のコンクリート柱の体感スペースは、ダニエル・リベスキントの設計、およびサシャ・ワルツの『ケルパー』で我が国でもおなじみの、ベルリン・ユダヤ博物館の一画にも設けられていた。となるとこの記憶は、二つの記念の場をつなぐ必然的なものとなる。身体感覚に深く訴える建築や当時をそのままに伝える遺産、展示の感性的な効果、当事者の生きること全体をカバーしようとする姿勢においても丹波マンガン記念館とベルリン・ユダヤ博物館は似ているのだが、国の犯罪に触れることに踏み込んだ記念の場という点でも一致する。
こういった共通点を踏まえた上で、目を向けなければならない違いが出てくる。方や世界的建築家を擁し、国際的な注目とともに未来へと踏み出すことに成功した国家規模の支援体制、方や2009年12月に閉館すると決めざるを得なかった家族経営。ここで、両国の文化政策や、国民一般の歴史観の根本的な違いをパブリックに批判することは必要だと思われる。けれども、筆者がこの記念の場に身を置いて考えたのは、この問題が、多くの日本人が加害の歴史に対して自らをうまく関係づけられないでやってきたのを反映しているんじゃないかということだ。それは身内から、これまで出会ってきた大人たち、そして今、彼らと同じような年齢と社会的立場にいる自分までを含めて。
◆ ふたたび、関係の場としてのミュージアム
ここで注目したいのは、それぞれの記念館に張り巡らされた関係が、生活史的な連関や、感性的な経路を経て、流動化される契機を孕んでいる点だ。前者が伝えようとする鉱山で生きること働くことと後者が扱う民族の歴史の全体には、一つの論理では捉えきれないものが含まれていて、そこではαとωが相対化し合うといったようなことさえ起こる。たとえば二つの場を覆う歴史的な対立関係(ユダヤ人とドイツ人、朝鮮人と日本人)において、被害/加害の関係は揺るぎない。そこには、ミュージアムにおける当事者と傍観者という関係も重ねられる。けれども、例えば働くという切り口一つをとっても、それを入り口に両者がなにがしかを共有したり、さらには関係を反転させることすら起こり得るわけで、その意味で、強烈なパーソナリティーを備えた媒介者のいる丹波マンガン記念館の社会的な意義はかなり高い。ともかく、はじめに述べたミュージアム-諸価値の係争の場-に身をおくことの可能性を繰り返すなら、そこで得られた諸々を、鑑賞者それぞれが抱える現実のポリティクスに置きかえてゆくことに、歴史を活性化し、未来の価値観をつくってゆく場としてミュージアムの可能性があるように思える。
◆ お知らせ
本文で触れた高嶺格さんの『在日の恋人』制作記録集と、丹波マンガン記念館についての李龍植さんの本が、現在出版準備中だそうです。関連情報は分かり次第お知らせさせていただきます。
|
|
|

|