 |
 |
 |
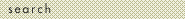 |
 |
|
|
 |
パフォーマー
|
 |
会場
|
 |
 |
公演日
|
|
| Rio. |
松岡永子 |
2003年に没した岸田理生の岸田戯曲賞受賞作『糸地獄』を再構成する試み。
『糸地獄』は少女・繭が糸屋へ行って女郎の中に母をさがすお話。完成している印象の強い作品をどう再構成するのか。 実際に見て、まあ、予想どおり。
社会性や政治性の問題意識は漂白され(「表では糸を売って裏では色を売る」という糸屋は「表では女工哀史裏ではからゆきさんの大日本帝国」のかなり露骨な喩だろうし、女郎屋には必ず御真影が掛かっている。その辺りがすべて抽象的になっていた)、土俗的なにおいからは足を洗って宙に浮いたキレイな舞台。アフタートークで宗像駿氏が「センスがいい」と言っていた。それはそうかもしれない。ひとつの美的センスでコントロールされた舞台であることは確かだ。あとは個人的な好みの問題か。
『糸地獄』の、特定の時代・土地の描き方は、そのままでは現代に通用しないだろうと思う。しかし、抽象化することで普遍性を獲得できるとも、わたしには思えないのだ。 岸田理生という作家は一般にどのくらい知られているのだろうか。最も有名な仕事は、藤原竜也のデビュー作『身毒丸』の台本(演出は蜷川)だろうか。
ちなみに、わたしは岸田理生の大ファンである。
OMSで『宵待草』を見て好きになった。もっとも見た舞台は数えるほどしかない(岸田事務所は関西での公演がほとんどなかった)。手に入る戯曲、小説を読み、脚本に名前があればTVドラマも見た。岸田理生は、それぞれのメディアに合わせて別のお話を語るといったタイプではない。語りたい宇宙は一つだけそこにあって、作品ごとにそれぞれの切り口を見せた(さすがにTVでは規制が強かったようだが)。
一方、hmpの演出家は、呼吸、動き、言葉など、使う要素は誰にとっても同じで、それをどう組み合わせるかを考えると言っていた。 どうしようもなく物語を吐きだし紡ぐ、という作り方から、要素をピックアップして組み合わせる、という作り方へ。
この差は世代差だろうか。
自分の手で紡ぎ織りあげた布を纏うという生活から、店頭で適当なアイテムをそろえコーディネートする生活へ。私たちの日常生活が生産から消費へとシフトしたように、作品をつくるということも、どのように組み合わせるかを楽しむ消費行動へと変わってきているのだろうか。
|
|

|