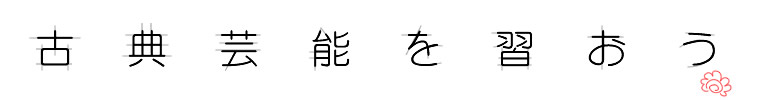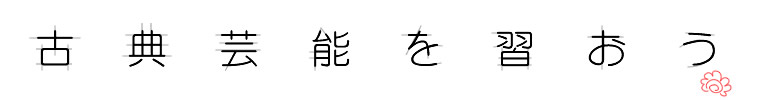|
—上方舞を習ってみたい、でも、どうしていいか分らない、そうした方って結構いらっしゃると思いますが…
若禄之「そうですね。この前も塾にいらした方が“お電話するのに物凄く勇気がいりまし
た”って、おっしゃっていたんですよ。敷居が高く感じられるのだそうです。私もその敷居を何とかしたいと思っております。
その敷居って、やっぱり情報がないってことなんですよね。私はある意味気負っているというか、舞が好きという純粋さとは別に上方の文化を次の時代に伝えて行きたいっていう思いがあるのです。
山村友五郎という創設者がこんなに素晴らしい振りをつけ、山村流がおこった天保5年(1834)から今日に至るまで、脈々と祖先によって受継がれてきたのですから、私もそれを次代に伝えていきたいと思うんです。だから、一人でも多くの人に知ってもらいたい、とにかくかじってもらいたいって考えています。
それと私が弟子に入った頃と違って、ただ“耐えなさい。お稽古して苦労しなさい”では、今の時代感覚からいうと、それでは難しいでしょう?
受継ぐものは受継ぐものとして、伝える手法は時代にあわせて工夫していかなければならないと思います。」
|