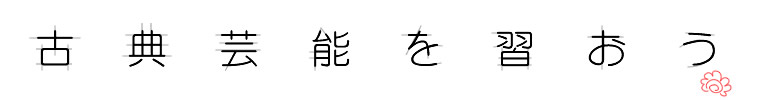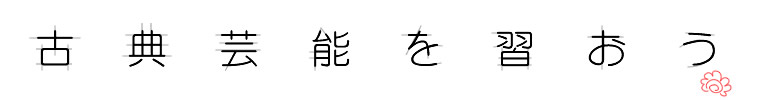|
地歌 澤 千左子(さわ ちさこ)先生
上方の地で生まれ発展した「地歌」。そして「上方端唄」。
上方端唄の中には流行歌のように気楽に楽しめるものが数多くあります。
しかし今、それを口ずさめる人って、大阪にはいったい何人いるのでしょう?
例えば近所で少しお酒を飲んだ帰り道、上方端唄を鼻歌に、酔い覚ましの風にあたりながらホホンと歩いて帰る…私はそんな人が素敵にお洒落で豊かに感じます。
一昔前でしたか、「ボクサーが部屋に帰ってピアノを弾く」っていうのが、「カッコイイ〜」とか、意外性のカッコ良さが注目された時期がありました。ボクサーになるのも、ピアノを流暢にひくのも、どっちもちょっと無理っぽいけど、パソコンを使う私達が、上方端唄を鼻歌としてなら、軽く口ずさむことは出来そうではありませんか(甘い?)?
古典芸能にふれること自体がスペシャルなのではなく、日常、古典芸能を身近にしているからこそ、舞台で観たプロの至芸が、「心に残るスペシャル」になるのではないか?と思います。
今も愛される古典芸能の多くは関西で生まれました。大坂の豪商がパトロンとなったり、庶民に愛されながら、その芸能は発展しました。
「大阪人になろう」は、大阪に住んでいるから「大阪人」というのではなく、大阪の文化を知った大阪の人になろうよ、という考えから企画されたものです。
その中では、上方舞の代表的な流派である山村流(1月24日25日)と、吉村流(3月6日)のご紹介もします。地歌、上方端唄も、従来のように舞の演奏だけではなく、トークを交えながら、親しんで頂くことを大切に、構成がされています。
今回は、その両方で、地歌の演奏とお話をして下さる澤千左子先生をお訪ねし、地歌を習うということについて、お話を伺ってみました。
|