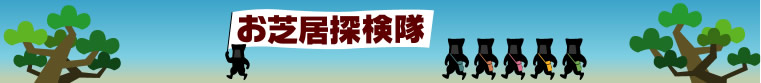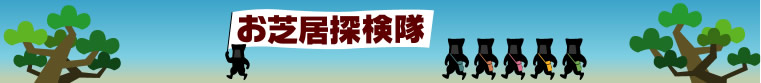|
上方ゆかりの俳優、足跡を訪ねて
お芝居探検隊の街を探索するシリーズは今回で10回目です。
それ以外にも、役者さんや関係者をゲストにお招きして、特別企画なる催しも開催してきました。
かって大阪は、歌舞伎俳優や力士ら、時のスターが住まいし、賑々しく文化を発信していました。歌舞伎文楽の名作の多くは大阪で生まれ育ったのです。ですから大阪には今もその芝居ゆかりの地名や標(しるべ)、名優達の墓碑などが数多く残っています。先般もある歌舞伎俳優さんとお話していたおり、「大阪には劇史として凄いものが沢山あるのに大切にされていないのでは?」というような、大阪人として悲しいご指摘を受けました。
芝居ゆかりの地を探索することはただ名残を懐かしみ、芝居に対する造詣を味わい深くするだけに留まりません。隆盛を誇った関西の歌舞伎が何故衰退期を迎えたのか・・・?現状に至るまでの過程も推察することが出来るはずです。
歌舞伎には日本人のアイデンティティーが色濃く描かれています。そして芸能は自国の文化を表現するのに、分かり易くかなり有効な手段です。国際化社会が叫ばれて久しい今日だからこそ、私達一人一人が自国、そして自ら住まう土地の文化を知っておくことが必要です。
今年は歌舞伎発祥から400年と云われています。
上方の地に名華を咲かせた名優達の足跡を節目の歳こそ偲んでみたい・・・私は少々コアな歌舞伎ファンなのでそうした考え方で探索をしてみますが、歌舞伎にあまり興味のない方でも、「あの芝居のこんなものがここにあったのか」と、初秋の大阪を楽しんで頂けたらと思います。
募集要項の後、簡単にコースのご案内をし、その後に、この次のお芝居探検隊特別企画で予定している催しのご案内をしています。この2つは関連した催しですので、続けてご参加頂くと上方の役者系譜がより鮮明に知り得ます。
お芝居探検隊 第10回
「歌舞伎四百年 上方ゆかりの俳優・その足跡を訪ねて」
歌舞伎名作の数多くは、大阪・道頓堀で生まれ育ち、歴史に語り告がれる名優達が、上方歌舞伎に名華を咲かせました。今年は歌舞伎発祥から四百年、大阪市中央区を中心にその隆盛を偲び、足跡を訪ねてみます。
日時:10月5日(日)1時出発(受付開始12:30)
集合:大阪市立 中央会館 06-3211-0630
地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」下車6号口より南東へ徒歩約6分
費用:500円(資料代含む)
案内:お芝居探検隊隊長 河内 厚郎 氏(文化プロデュサー・愛する会世話人)
主なコース:
中央区 八幡筋 お染久松油屋跡
谷町8丁目 近松門左衛門の墓→
中央区中寺 妙徳寺(二世三世中村梅玉)→薬王寺(七〜十一世片岡仁左衛門・初代中村富十郎)他
→法性寺(「鰻谷」八郎兵衛の墓)→圓妙寺(実川延若代々、三桝大五郎)他→久城寺(「曽根崎心中」
お初の墓)→正法寺(初世三世中村歌右衛門、三世中村芝翫)他→常國寺(初代中村鴈治郎・四世中村歌右衛門)他→
天王寺区 西方寺(初代中村魁車)→一心寺(初代市川右團治・二世三世阪東寿三郎・中村宗十郎)他
中央区 笠屋町(白井松次郎・三世翫雀・初代右團次・初代二世延若などが住まいし、八世團十郎が自決した旅館植久などがあった)→玉屋町(初代鴈治郎住まい)→相生橋(心中重井筒)→宗右衛門町(中村宗十郎が呉服屋)→鴈治郎横丁→上方浮世絵館
申込み:往復ハガキお1人に付き1枚で、住所・氏名・年齢・電話番号をご記入の上、下記迄お申込み下さい。
〒540-0012 大阪市中央区谷町2-7-6 みのるビル401
関西・歌舞伎を愛する会「お芝居探検隊10/5」係
締切り:9月18日(木)消印有効
主催:大阪市文化振興事業実行委員会 協力:関西・歌舞伎を愛する会
|