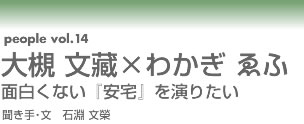 |
 |
今日の「能楽NOTE」では、復曲の話をされていましたが、今後の復曲や新作の構想などをお聞かせください。
大槻「新作をね、堂本正樹さんが、ゲーテの戯曲を三島由紀夫が翻訳した『ファウスト』を能にしたいって、ずっと仰ってるんだけども、今、堂本さんのお身体の具合がねえ。だから、なかなかすすまなくて」
堂本正樹さんは、新作能『蛙ヶ沼』の作者でもある。今日の能楽NOTEでも話題にのぼっていた『蛙ヶ沼』には、沼でたくさんの蛙が鳴いているところを、従来の能にはなかった輪唱などの手法を使って表現する場面がある。
 今日の「グエイグエイ、ギョウギョウ(蛙の鳴き声)」ですが、わかぎさん、えらいツボにはまってはりましたよね。 今日の「グエイグエイ、ギョウギョウ(蛙の鳴き声)」ですが、わかぎさん、えらいツボにはまってはりましたよね。
わかぎ「あれ、いきなり来たぁ!(笑)めっちゃいきなり攻撃されたんです!だって、(謡本を)持ってはるのに、自分からは何も言わはれへんから、なんで持ってはるんかなと思ってて。最後に尋ねたら、いきなり来たから、やられたぁ!って」
あれ、ちゃんと漢字が当てはめてあるんですよね。
大槻「そう。“ぐ”は“愚”、“えい”は“詠”、“ぎょうぎょう”は“業々”」
わかぎ「ほおぉ」
漢字を見ると、なんとなく思想が感じられるんですが、何も見ずにいきなり、カエルの鳴き声を謡で謡われると笑いますよねえ。
わかぎ「何も前振りしはれへんまま、いきなり…(笑)」
本題に戻そう。
今までたくさんの復曲や新作を手掛けて来れられて、いろいろなパターンがあったと思いますが、これからどういう傾向のものをなさりたいと思っていらっしゃいますか?例えば、梅若六郎さんなら、ショー的な能の復曲が多くて、声明を入れたりパイプオルガンを使ったり、イリュージョン演出をMr.マリックさんがなさったりしていますね。
大槻「僕はね、復曲したり新作したりした作品は、(初演者以外の)他の人が演っても成り立つっていうのが大事だと思う。新作というと、能の範疇をギリギリ超えるか超えないかというところまでいってしまうから、他の人が演るのは難しいと思うけど。まあ、新作はそれでもいいけど、復曲は、他の人でも出来るようにしておかないと、せっかく復曲しても、また演らなくなってしまう。」
わかぎ「復曲した意味合いみたいなもの?」
大槻「うん。あ、そうだ。今度、京都のアルティっていうホールで、『渇水龍女』っていう復曲のものをするんだけど、演出するの」
わかぎ「演出しはる?!…ちょっと嫌そうなお顔ですけど(笑)」
演出はお嫌いですか?
大槻「いんや」
わかぎ「でも、しんどいですからねえ」
演出だけですか?ご出演は?
大槻「演出だけ」
わかぎ「(演出家の)形から入ってくださいね!こう、サングラスとかかけて(笑)。とりあえず、形から!」
京都府民ホール・アルティって、舞台がユニット式になっていて、動かせるんですよね。下見をなさっていかがでしたか?
大槻「うん、いろいろ。でも、裏が狭いのでねえ…」
使い勝手というのはやはり実際行ってみないとわからないものですね。新しいホールを作るときに、役者さんたちの意見は反映されないんでしょうか。意見を求められたことはありませんか?
わかぎ「ないですねえ。初めてのホールなんか、行ってみて、うそぉ!こんなとこに階段あるで〜!みたいな。邪魔やん〜て」
能楽堂は、もちろん能楽専用の舞台だが、驚いたことに、役者自身が所有者もしくは経営者ではない施設については、役者側の意見が反映されていないケースがほとんど。一般の劇場についても使用する側の意見はほとんど反映されていないようだ。 |
|