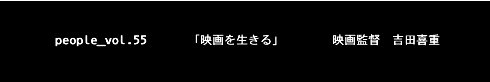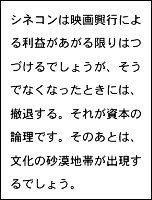 話は変わりますが、全国各地にシネコンができた結果、地元の劇場がどんどんつぶれて、シネコンだけになっています。シネコンでかかる映画が、必ずしも観たい作品、ぜひ観てほしい良質の映画とは重なりません。そして、資本の論理によって利潤を追求するシネコンは、その資本が撤退すると、シネコンもなくなってしまいます。そうすると地元には、なにも残らない。そういう危機感から、ここ数年の間に、全国の各地域で、新しい自主的な上映活動をしてゆこうという「コミュニティシネマ」の機運が、非常に高まっています。我々も、そうした「コミュニティシネマ」のひとつとして上映活動をしてゆこうとしているのですが、そういった動きに関しては、どのようにお考えでしょうか? 話は変わりますが、全国各地にシネコンができた結果、地元の劇場がどんどんつぶれて、シネコンだけになっています。シネコンでかかる映画が、必ずしも観たい作品、ぜひ観てほしい良質の映画とは重なりません。そして、資本の論理によって利潤を追求するシネコンは、その資本が撤退すると、シネコンもなくなってしまいます。そうすると地元には、なにも残らない。そういう危機感から、ここ数年の間に、全国の各地域で、新しい自主的な上映活動をしてゆこうという「コミュニティシネマ」の機運が、非常に高まっています。我々も、そうした「コミュニティシネマ」のひとつとして上映活動をしてゆこうとしているのですが、そういった動きに関しては、どのようにお考えでしょうか?
おっしゃるとおりです。おそらくその地域の人たちと文化的なコミュニケーションをするという意識はないでしょうね。シネコンは映画興行による利益があがる限りはつづけるでしょうが、そうでなくなったときには、撤退する。それが資本の論理です。そのあとは、文化の砂漠地帯が出現するでしょう。たとえ現在シネコンがあっても、その地域のコミュニティが、映画を上映している独立館を、いまから支えていないかぎり、シネコンが撤退してから始めようとしても遅いのです。
東京でもそうですが、そうしたシネコンにどう対処してゆくのか。疎外されて孤立無援であっても、文化としての映画に志をもっておられる独立館、景山さんのように、かつての日本映画をよく知っておられる方たちを、地域社会が積極的に支えてゆくことが大事です。それは一方的に中央から流されてくるコマーシャル・ベースの作品を、地域のコミュニティが見返すといっても良いのかもしれません。今回の上映キャンペーンも、映画を作る側の私たちも地域のコミュニティと直接ふれあう場をもち、孤立無縁な独立館の状況を、すこしでも打破できればという気持からです。

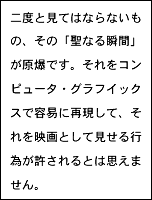 いま、地方で、町のなかに空き家がいっぱいあるという空洞化現象がおこってます。そんな空き家や空き家同然になっている場所を、地元の商店街が買いとるかたちで、映画上映をおこなえるような空間にできたら、と思ってるんです。こうした動きは、たとえば高崎映画祭のスタッフたちが中心になって、銀行が撤退した場所で、新しい映画館を今年中に造るらしい。そうした動きが、今後も各地でおこってくると思います。そのときは、ぜひご協力をお願いします。 いま、地方で、町のなかに空き家がいっぱいあるという空洞化現象がおこってます。そんな空き家や空き家同然になっている場所を、地元の商店街が買いとるかたちで、映画上映をおこなえるような空間にできたら、と思ってるんです。こうした動きは、たとえば高崎映画祭のスタッフたちが中心になって、銀行が撤退した場所で、新しい映画館を今年中に造るらしい。そうした動きが、今後も各地でおこってくると思います。そのときは、ぜひご協力をお願いします。
もう一度『鏡の女たち』の話にもどるんですが、14年ぶりでしかも原爆をテーマにしたこの作品は、いま、各地で上映活動がはじまってます。年内に、ビデオ・DVDも発売されますが、これからご覧になります皆様に、ご紹介していただけませんか。
私が原爆をテーマにした映画を作ると表明したとき、映画のメディアも、私の親しい友人たちも、なぜ半世紀以上もたったいま、原爆なのかと、疑問をもつ人が多かった。半世紀以上が過ぎたいま、なぜ改めて原爆を問いただすのか。もちろんそれは原爆、あるいは戦争に反対するためではあるのですが、それと同時に私は映画監督ですから、原爆を映画として描くことがどういうことであるのか、それを問いかけつづけながら、迷いに迷った結果、50年かかってしまったのです。
このように私が迷った理由は、原爆を映画によって語り、それを描く権利をもっているのは、犠牲になった人びと、死者だけだと思えてならなかったからです。あの時、広島、あるいは長崎に、私はいたわけではありません。そこにいなかった人間が、原爆を想像し、イメージだけで描くのは、原爆の犠牲者、死者の方たちへの冒涜ではないのか。そのように思えてならないのです。人間はみずからの自由な想像力によって、あらゆることを描くことができると自負するかもしれませんが、そうした想像力にしても、描けないものがあるとすれば、それが原爆なのです。そして、私には原爆を描く権利がない。
もっとも私自身にも、終戦の夏、生まれ故郷である福井で大空襲にあい、猛火のなかを逃げまどい、ようやく生き延びた記憶があります。広島のすさまじさは知らないにしても、私のなかにある戦争の記憶、その恐怖といったものは、広島と深く重なり合っているともいえるのです。広島という地名は、戦争のすさまじさの象徴です。広島を思い起こすことは、私の福井を思うことでもある。それが私に原爆を描かせた理由ですが、果たして被爆体験のない私に、想像力に頼ってそれを描いてよいのか、そうした迷いを乗り越えるためには、私には50年の歳月が必要だったのです。
たしかに『鏡の女たち』は、原爆をテーマにした作品ですが、ぜひ観客のみなさんに見ていただきたいのは、それを描く権利のない私が、原爆を映画のなかでどのように描いたかということです。8月6日の、あの瞬間のキノコグモを、コンピュータ・グラフイックスで描くことは、技術的には簡単です。しかし、それは原爆投下の瞬間を、再現したに過ぎません。これまでもそうした映画がありましたが、原爆は再現できない、再現してはならないとものだと、私は考える人間です。二度と観てはならないもの、その「聖なる瞬間」が原爆です。それをコンピュータ・グラフイックスで容易に再現して、それを映画として見せる行為が許されるとは思えません。
それではどのような方法で、8月6日のあの瞬間を描くのか。私が映画のなかで原爆を見せるのではなく、それを見る観客自身が、それぞれの想像力によって、おのずから8月6日の原爆を映画のなかに見てしまう。そういう映画なら作れる。私が原爆を見せるのではなくて、観客のみなさんがこの映画をとおして、あの瞬間をイメージ化し、みずから追体験してしまう。それはみなさんの想像力によって、観客自身がみずからの原爆映画を作ることでもあるのです。
『鏡の女たち』は、昨年の朝日ベストテン映画祭第1位を受賞し、これまでの監督のお仕事の到達点、集大成というような高い評価をされていますが、どのように受け止められておられますか?
この作品への暖かいご支援をいただいて、感謝しております。
私はこの14年間、映画から離れておりまた。いまの若い世代の方たちは、同時代的なものとして、あるいは同時進行的に、私の映画を見ていないわけです。そうしたことを踏まえて、私の親しい友人である蓮實重彦さんや、四方田犬彦さんたちが、『鏡の女たち』を契機に、いわば吉田喜重の回顧上映を行い、再評価の場を作ろうと努力してくださったのです。もっとも回顧上映というのは、その当事者が亡くなった折りに試みられるのが普通ですが、それが私の場合は、生きながらにして回顧上映をしていただける(笑)。大変幸せなことだと思っています。
東京では9月11日から3週間、全作品19本と主なドキュメンタリー作品が、蓮實さんのネーミングによる、「吉田喜重 変貌の倫理」として、特別上映されました。また大阪でも、この12月4日より2週間、第七藝術劇場でで上映されます。その折りには、私も岡田とともに、劇場でトークをさせていただきますが、45年にわたる私自身の映画人生を語ることができればと思っております。
 確かに回顧上映は、監督が亡くなってからが多いんですが、お元気なうちに、監督ご自身がそこに立ち会われ、直接言葉を発せられるというのは、観客としては、大きな魅力だと思います。 確かに回顧上映は、監督が亡くなってからが多いんですが、お元気なうちに、監督ご自身がそこに立ち会われ、直接言葉を発せられるというのは、観客としては、大きな魅力だと思います。
ただトークといっても、これは私の持論ですが、作品の一作、一作が、こういう意味で撮りましたという話にはならないでしょう。デビュー作である『ろくでなし』にしても、それが封切られた60年当時の観客の見方と、現在の若い世代の受け止め方が、当然ちがうでしょう。それがこの映画への新たな対話の始まりになれば、それこそ45年以前の映画が、いまも生きている証拠です。
こうした場合、監督自身がこういう意味で、この映画を作りました、こういうふうに見てくださいと話すことは、観客の映画を見ることの歓びを奪うことにもなります。ただ私なりに、この映画をこのように作らざるを得なかったというトークでしたら、許されるでしょう(笑)。
|