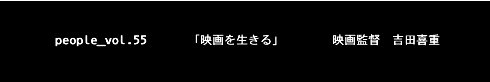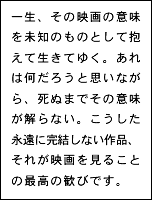 この前の小津シンポジュウムのとき、日本から出席した監督たちが、欧米の評論家から逆に、「テーマについて語らないことが、驚きだ」と言われた。実際、日本の作家の側からすると、そういうテーマを語れる時代でもないということでしょうか? この前の小津シンポジュウムのとき、日本から出席した監督たちが、欧米の評論家から逆に、「テーマについて語らないことが、驚きだ」と言われた。実際、日本の作家の側からすると、そういうテーマを語れる時代でもないということでしょうか?
それは私の世代の日本映画を見てきたから、「テーマについて語らない」という発言があったのでしょうが、映画監督はそれぞれが生きた時代と、無縁であることはできません。いまの40代以降の監督は、8mmで自主映画を作った経験をもとに、監督になるケースが多い。撮影所育ちではないわけですから、既成の映画監督の演出を直接見てはいない。その意味では、まったく自由です。映画を見ることと平行して、非常に早い時期から8mm映画を作っている。テーマについて考える前に、自分の眼や手が、おのずから映画を作ってしまっている。
私の世代ですと、矛盾した現実を前にして、何故そうなのかと考えざるを得ない。あるいは自分と時代との関係を考える。それが映画のテーマとして追求され、シナリオとして書かれてゆくのですが、8mm世代になると、まずシナリオを書く前に、8mmカメラを回している。そして映っているものから、テーマを発見しようという感覚なのでしょう。もっともテーマがなくても、映画は成り立つものです。
ドキュメンタリーに近づいてゆくんでしょうか?
そうともいえますね。考える前に、行動してしまうというか、カメラを回してから、初めて考えるのですから、私の時代とは転倒している。あのころは映画のカメラは、映画企業が独占しているようなものでしたから、個人で映画を撮るとは不可能と思われていました。いまは撮られてしまった映像を見ながら、初めて考えるのですから、ドキュメンタリーに近いといえるでしょう。
以前は映画を作ることは、きわめて特殊なことであって、見ることが主体でした。それが良い映画だと思えば、もう一度見るしかない。そして新しい発見をすると同時に、また新たな謎が立ちはだかってくる。そのために、さらに同じ映画を見る羽目になる。一生、その映画の意味を未知のものとして抱えて生きてゆく。あれは何だろうと思いながら、死ぬまでその意味が解らない。こうした永遠に完結しない作品、それが映画を見ることの最高の歓びです。
『秋津温泉』や『水で書かれた物語』などを観ても、あの最後をどう受け止めたら良いのか、と思いました。映画のなかでは完結していない、あとは観る者に託されている、というか。たとえば『秋津温泉』の彼女のあの生き方は、いったい何だろうか、って。そういうことを監督の作品を観て、感じていたと思うんです。
小津さんの生誕100年のシンポジュウムでも、小津さんの映画を見て、8mmのカメラで同じようなローポジションで撮ってみて、その映像を見ながら、これは何だろうと考えたという発言がありました。私たちの場合は、映画のスクリーンは遠い彼方のものでしたから、映し出されるロー・ポジションの意味だとか、なぜ人物を正面から撮るのか、そうした疑問は想像力によって解決するよりなかった。それがいまは、自分で映像を撮ってみて、何だろうと考えるわけですから、ただちに答えが見出せるのかもしれませんね。
そういう作り方になっている。それは結果的には、生活のディテールに関心がいってしまいますよね。
現在もかぎりなく矛盾に満ちているはずですが、それが日常生活のなかで見えにくくなっているのは確かです。極端な例をあげるようですが、いま憲法を改正すべきだという論議がなされています。しかし戦後新しい憲法が制定されたとき、反対する人はいなかった。それは旧帝国憲法より、はるかに人間の自由を保障し、平和を願う憲法であったからです。それがいまの憲法改正論議は、アメリカによって強制されたものだからだとか、自衛権や国際貢献に矛盾があるとして、憲法の改正が問われている。それはかつてのような大きなテーマとしての憲法ではなく、小さなテーマとしての憲法論議ともいえるでしょう。憲法は人間が作り出したものですから、完全なものではないにしても、それが言葉で書かれている以上、それを解釈しながら、生かしてゆけるかどうか、それは私たちの心の問題です。そしていま、憲法改正を小さなテーマとして、改正論議されるなかで、戦後最大のテーマが矮小化されてゆくことに、私も強く懸念する一人です。だからといって、大きなテーマが語られる時代が良いといっているのではありません。それは不幸な時代を意味しており、かつてのような激しい時代変革は、二度と起こしてはならないからです。そして大きなテーマから開放された現在、小さなテーマとしての映画をどのように追求するのか。日常のデテールに眼を凝らすことから始まった、8mmカメラの世代には、それが可能なはずです。
|