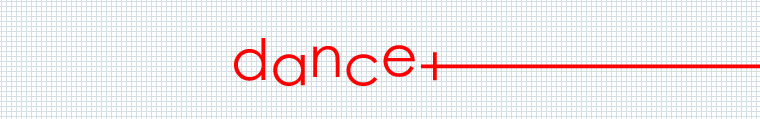
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
|
『テーパノン/Thep-pranom』クロスレビュー:藤田一×dance+メガネ
choreography : ダンスを書くことと書かれたダンスをなぞることの間
執筆者:メガネ
「書く/描く」という身体技術を自分のものにしたときの感覚を憶えている人はどのくらいいるだろう。ましてそのプロセスとなれば、思い出せる人はほとんどいないのではないか。特に、ひとたび身につけてしまえば、この技術を用いることのほとんどが記号の操作、つまり頭仕事と摺り替えられてしまう、鉛筆や筆を動かす行為の原点にアクセスすることは容易ではない。
ピチェ・クランチェン作『テーパノン/Thep-pranom』は、この誰もが知るが、結果として得られてしまった後では意識下に埋もれてしまう、「書く/描く」という技術の習得にまつわる経験を想起させる。そしてその身体の記憶を一つの回路として、ダンスを習ったことのない者にも、ダンスの成立を体験させる。そんな可能性をこの作品は潜在させている。
|

| | |
写真:阿部綾子
|
冒頭、ダンサーたちは、三方の壁と床を黒板に見立て、線や図像や記号を書きつけてゆく。この場面は、作品への3通りのイントロダクションとなっている。
一つには、タイの古典舞踊コーン(Khon)の基本型、テパノン(Theppanom)の思想の図解。あたかも講義中に教師が行う板書、あるいは学生がとるメモのように書き連ねられる言葉やシンボルは、テパノンにもとづく作品コンセプトの一端を、鑑賞に先立ち与えてくれる。だが、それらの意味するところは、作品が紡ぐ時間の体験を経なければほとんど無に等しい。
並行してチョークの先から生み出される線の大部分は、意味の限定されないシンボルや曲線になる。これらは目の前で展開される舞踊を、純粋に視覚的なかたちとして把握するためのオリエンテーションとなるだろう。だがそれが主眼なら、「見る」という身体機能を外化し、分析し、操作することに長けた映像のほうが効果的だ。例えば、微細な動きに注意を促すため、微風に震える朝顔の大写しの映像をスローモーションで流したある作品のように、映像で目の構えを準備するコンテンポラリー・ダンス作品も少なくなくなった。
では手書きの線が作品の中で担う一番大事な働きとは何なのか。少なくとも、頭と目のためのオリエンテーションではない。
チョークを手放したクランチェンの演技を追ってゆけば、それらの線描と踊る身体との何がしかの結びつきが見えてくる。フロア・パターンで言えば中央から4つの際に沿って舞台を一周した彼の道行きを、順に見てみよう。まず真ん中の四角の上で足を踏み、三角のシンボルでテパノンの思想を図解した下手の壁沿いを、客席に向かってシンプルな基本姿勢で前進。今度は上手の壁手前に力強く描かれた円に近づいてゆきながら、円の内外にうねる曲線をなぞるような手の動きを見せた。同様に、上手の壁沿いでは、移動に沿って流れるように描かれた曲線が、奥の壁沿いでは、相対する下手の壁の奥に描かれた山河のように見える大きな三角が、3次元の空間に展開されたように見受けられた。壁や床に描かれたたシンボルは、ダンサーが身体で解釈し生を吹き込む2次元のコレオグラフィーだったのである。
さらに、2次元、3次元のコレオグラフィーは、このダンスの記譜の分析や解釈の「結果」を観客に与えるのではない。ダンスの分解と統合が伴う時間は、見る者に何をもたらすのだろうか。
後半の構成を眺めるなら、四角、三角、円のシンボルを経由し三角の図像に到達したクランチェンの踊りは、古典舞踊の習得から本作品制作に至るまでの、何がしかパーソナルな歩みと結びついているようにも見受けられる。もし、この道行きが実際のテパノンの習得過程に対応していたなら、終盤でウィリアム・フォーサイスのソロを想起させる(言い過ぎ?)自由なスタイルへの移行を見せたクランチェンの道行きは、彼がダンスと取り組んで来た過去の時間を包括するものと読めるだろう。そのような目で見れば、その傍ら遂行された他のダンサーの演技も同様に、各々の身体技術の習得過程からこのワークショップへの参加に至る時間を反映するものだったのかも知れない。
最後に全員がテパノンの足踏みをそろえると、それまで個々の時間を紡いでいた彼らが、一つのリズムを共有する。この締めくくりは、彼らが共に過ごした時間を示唆すると同時に、パフォーマーたちが『テーパノン』制作に参加することで到達した「出発点」と、今後の展開を寿ぐかのようにも見える。異なる背景で身体技術を身につけてきた彼らの共同制作の成果としては、できすぎた構成だ。
|

| | |
写真:阿部綾子
|
とはいえ、仮に踊りがこのような順序で進行していたとして、観客は、パフォーマーがたどったプロセスを追体験できはしない。観客に与えられるのは、2次元と3次元のコレオグラフィーの間、そして線をなぞることとそれらから解放されることとの間を行き来する間に身体が見せる、諸々の相である。そして、それらが見る者の身体と響き合う瞬間がもたらされるのであれば、先に述べたパフォーマーにとっての事実と作品との対応関係など重要ではない。諸々の時間をたどり直すという作業は、そのような瞬間から始められたのであって、それなしに作品を再構築しても、体験を事後的に捏造するだけである。
では本作は、踊る身体の時間とそれを眺める者の時間がシンクロする瞬間をどのようなやり方で招いたのか。
私的な想起を手がかりにすれば、クランチェンの踊りを追う中で、筆者は幼少期に放り込まれた書道教室で、手本をなぞることから解放された時の風景をありありと思い浮かべた。ちなみにこの出来事は、長らく、年老いた厳格な先生に珍しく褒められたエピソードと、書いた文字の出来上がりのイメージに摺り替えられて記憶されていたものである。端的に言って、誰もが識る「書く/描く」ことをめぐる身体技術のトレーニングのプロセスが目の前で展開されたことにより、この想起はもたらされたと言える。
この想起をダンスに結びつけるために、もう一つ私的な経験を参照したい。誰もが共有できるものではないが、書くことと踊ることが結びつく地点を指し示してくれるから。それは、ある振付家が遺したコレオグラフィーを研究していた時のこと。この作家が、あろうことか作品のほとんどを占めるマイムを速記で残していたため、作品の再現に固執した筆者は、すでに使われなくなった速記法を稽古する羽目になった。研究結果はさんざんだったが、正統な書法とそこからの振付家の逸脱を自らの手でなぞった筆者には、今日ではダンスの科学的な分析ツールとして捉えられている記譜が、その原点においてはダンスと非常に近い感覚で生み出されていたという直感が残された。ちなみにこの速記を考案した ガーベルスベルガーは、「文字とは空間における運動を紙に転写したものである」といったことを述べている。
まとめると、かなりの時間をかけて行われたドローイングは、空間に線を描く術であると同時に、本来的な意味で「コレオグラフィー」であることにより、異なる記憶を秘めた見る者の身体を、ダンスが始まる地点へと誘っているのである。
ここでさらに注目されるのは、描かれたシンボルがそれぞれ異なる論理を表していた点だ。俳優が描いた三角のシンボルは、言葉と結びついた思想を直感的に理解させる。男性ダンサーが数字を振っていった四角は、空間を合理的に分割する。対して女性ダンサーは、言語や論理から解放された純粋な曲線を束ねて円とする。つまり、クランチェンの演技が誘うダンスは、これら3つの要素を合わせて成り立っている。逆に言えば、ドローイングは彼が習得したダンスの要素を分解して提示したものだった。
作中のすべての時間は、この要素の分解と統合の過程と結びついている。それは、クランチェンがコーン舞踊と取り組んだ私的な時間、さらにはコーン舞踊の生成と解体の歴史に及ぶ広がりを示唆している。通常、踊るという行為の中では、こういった諸々の時間はなしくずしに一つになっている。なしくずしという言葉は悪いが、それは秀でたダンサーの必然だ。だが『テーパノン/Thep-pranom』においては、ドローイングの場面で、諸要素が分解されて与えられたことにより、観客は、先の瞬間を出発点に、複数の時間を織り上げた身体の歴史をたどり直す可能性を手にしている。
コンテンポラリー・ダンスの観客は、ダンスに限らず、共同体と結びついた身体技術を一つとして共有していない。その前で、どこかの共同体で形成されたダンスがいくら美しく踊られても、「異文化の理解」が席の山だ。そして「異文化理解」とは、同時に一つの理解の壁である。だが、手本の線をなぞる、そこから独自の筆跡や様式を生み出すという体験に、国境はほぼ存在しない。その意味で、クランチェンの『テーパノン/Thep-pranom』は、書く/描くことと踊ることを鮮やかに結びつけ、身体の記憶を手がかりとして、観客をダンスが潜在させる壮大な連関へと連れ出すように思える。
|
|
|

|