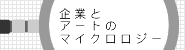
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
|
●「より完璧な技術で関わってもらうために」−やなぎみわ さん(yanagi miwa)
|

| | |
1967年 神戸市生まれ
京都市立芸術大学工芸科、同大学院美術研究科修了
アーティスト。在学中よりファイバーなどを使ったインスタレーションを制作。1993年よりCGを用いたエレベーターガールや案内嬢の写真・映像作品、「エレベーターガール」シリーズを発表し、国内外の展覧会に参加。2000年から彼女と同世代の女性が半世紀後の自分に扮する写真作品「マイグランドマザーズ」シリーズと実際の年配の女性が祖母の記憶を語るビデオ作品「グランドドーターズ」などを制作している。
最新作は寓話に基づいた写真と映像による「フェアリーテイル」シリーズ。2004年、グッゲンハイム美術館(ベルリン)を皮切りに巡回展がスタートし、国内では個展「少女地獄極楽老女」(丸亀猪熊弦一郎美術館)を開催した。2005年6月には原美術館で個展の開催を予定している。
やなぎみわHP: http://www.yanagimiwa.net/
辻(以下[T])−
本日はお時間いただきありがとうございます。早速ですが、やなぎさんが今回のインタビューにあたって、アクリル加工を依頼している株式会社モリヤとの関係は「アーティストと企業」ではなく、『アーティスト×技術者』という視点からしか話せないとおっしゃられたのはなぜでしょう?
やなぎ(以下[Y])−
「企業とアーティスト」として見るなら、株式会社モリヤと私は、加工の依頼をして代金をお支払いする、単なる業者と客、という関係になりますよ。企業というのは利益を追求することがその活動の目的であり、当然ながら何をサポートするにしても何らかの見返りが必要です。
アーティストが企業から「メセナ」活動を受ける時には必ず、アートに新たに価値を作り出して経済利益を得ようとする企業と、それに依存しつつ搾取されまいとする作家の完全なギブアンドテイクの駆け引きがあります。
しかし、作品の加工をお願いしているモリヤさんと私はマクロであろうとミクロであろうと「企業と作家」の立場でせめぎあいをしたことはありません。『技術者と作家』の立場で話し合い、作品の技術向上のために協力して頂いたら感謝し、株式会社モリヤに代金をお支払いする、当然の事です。
T−
「メセナ・協賛」と「協力」を混同するのは、日本のアートの状況を好転させないですね。
Y−
全く別のものは、きっちり分けて紹介すべきです。
メセナとも個人的趣味とも言い切れない、「企業としての自覚のないところで行われている細やかな活動」を『企業の活動』などと呼ぶのは誤解を招くことになります。
T−
そもそもモリヤさんに仕事を依頼するようになった理由というのは?
Y−
モリヤさんは写真現像の老舗ラボである「堀内カラー」さんからの仕事を多く引き受けていた写真の加工会社です。堀内カラーに写真現像を出すようになり、やがて写真をCプリントで仕上げ始めました。そして、ずっとしたいと考えていたアクリル加工のお金を払えるようになった97年ごろから自然とやり取りするようになってました。その頃はまだ、工場長の山口さん、営業の島川さんとも直接関わってはいませんでしたね。
T−
もともとは、モリヤさんとのやり取りは堀内カラーさんを介してなされていたのですね。
Y−
そうです。当初はどんな工場で作業が行われているのか、全然知りませんでした。堀内カラーさんで現像された写真が、私の依頼内容とともにモリヤさんに渡って、それが堀内カラーさんに戻ってきたら確認するという作業が続いていました。堀内カラーさんから、私がお願いしたことが伝えられていくのだけれど、私の場合、最後のアルリル加工という仕上げ工程は重要ですから、直接現場と話した方がいいだろうと。作品を広告のように一時的に展示するために加工するのでないことを理解してもらおうと、何度も工場に直接訪れて交渉説明しました。
|

| | |
T−
でも、別段アートに興味がない方に対して、広告とアートの違いを口頭で説明してもすぐに理解を得られるとは思えませんが。
Y−
そうですね。例えば美術館が作品を購入した時に、モリヤさんの工場から直接、展覧会の会場である美術館に運んできてもらうなどしました。それは、 直接学芸員の方と話してもらうことも、何を求められているのかを共有できる状況をつくるために必要だと考えたからです。
運び入れるだけかと思ったら、突然、学芸員の人に「船便を使って海外に作品を貸し出す場合は、このアクリル加工はどのぐらい耐えられるのか」など具体的に質問されてびっくりされたことと思います。広告物に求められる耐久性は長くて1ヵ月〜数年です。かたやアート作品は何十年も保つことが問われます。そこが大きな違いですから、モリヤさんとしては「そんなこと急に言われても」というとまどいはあったでしょう。申し訳ないとも思いましたね。
|
|
|

|