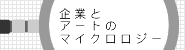
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
T−
気を遣いつつ、モリヤさんの通常のお仕事ではないようなことも依頼したのですね。こうしたやり取りをモリヤさんと続けてこられたのはなぜでしょうか?
Y−
それはもちろん作品を仕上げるためというのが一番の目的です。そして、日本には、私が望む質でこうした加工をお願いできるところがまず少ないという状況があります。当時は、モリヤさん以外ほとんどなかったといえます。だから、言い方は悪いですが交渉し続けるしかなかった。
T−
現在は、やなぎさんの求め続けてきたクオリティーを十分に理解してくださるようになった?
Y−
もう、お互いが一定の共通認識を持てるようになるにはコミュニケーションをし続けるしかないです。
そうして今、モリヤさんは、作品の作り手である私以上に作品の仕上がりに気を遣って頂いてます。
アクリルと写真の間にゴミが入らないように、他の作業が全て終わった夜を私の作品を加工する時間に充ててくださり、誰が見ても気付かないような小さなよごれが加工の過程で入ってしまったら「どうしましょうか!?」と、丁寧に電話を掛けてきてくれます。本当に今はいい関係を結ばせてもらっています。 自分で言うのもなんですが、工場に足を運び、工場長の山口さんや島川さんと会う努力をくり返したことが、こうした関係を結ぶために大切だったなと思います。
T−
一般的に、作品のチェックなどのために工場に足を運ぶことは珍しいのでしょうか。
Y−
他の方は知りませんが、通常はラボである堀内カラーさんに任せておいても、的確に依頼を伝えても下さります。でも、エレベーターガール、グランドマザーズシリーズにしてもそうですが、私にとっては、写真の前面にアクリル板を貼る=作品とアクリルが一体となると考えられます。それだけ、モリヤさんに依頼する加工の作業は、本当に大切なのです。
|

| | |
「エレベーターガール」シリーズ
|
T−
やなぎさんは学生のころは工芸科に所属されていました。その時は全てご自身の手作業で作品をつくられていたと思います。それが、写真というメディアを使うようになり、全く違う人間の理解を求めながら作品を完成させることにジレンマはありませんでしたか?
Y−
ジレンマはなかったですね。工芸科で着物の作品をつくった時、最後の手縫いまで全て自分でやっていましたが、その時も「縫い」のプロがした方が上手だろうなって考えていましたから。
作家次第だと思いますが、私は最後はプロの技術を借りることでより完全に近付けるならその方がいいと考えています。だから、そうする限りはより完璧な技術で関わってほしいから、いろいろな依頼もするわけです。
T−
やなぎさんがそうした技術に対してOKを出す瞬間というのは、どれほどの質の場合なのでしょうか?
Y−
それは、実物を前にしないといえませんね。言葉で説明するのはとても難しい。
T−
やなぎさんは海外でも多くの展覧会に参加されていますが、その場合は現地の業者さんに加工を頼むこともあるのでしょうか?
Y−
それはもちろんあります。これまで、フランス、ドイツ、アメリカなどのアート作品専門の加工業者にも依頼しました。広い作業場や高い機材をもっていたりするのですが、モリヤさんの仕事はそこにひけをとるものではありませんね。
とにかくマスプロダクションに関しては、印刷や加工の技術はどんどん海外に回されています。
しかし作品制作のための高い技術は、やはり近しいところにあって欲しいです。
また写真作品が多く作られるようになって、フォトラボや加工業者なども、アートの仕事が確実に比重が高くなってきているように思います。
T−
経済的な変動に左右されにくいのが、クオリティーを追求していく人たちのニーズですよね。
やなぎさんがモリヤさんにさまざまな事を求めたことが、結果モリヤさんの現在の技術につながっているとも考えられます。
|

| | |
「グランドマザーズ」シリーズ
|
Y−
私の場合、撮った写真をコラージュ合成した後にビッグプリントで焼いています。
それなりの技術を得ようとした時には、やはりそれ相応の対価を支払うことは当然だと思います。
T−
これほど作り手として「見せる」こと、「見え方」を追求し続けるやなぎさんにとって、作品を他人に見せるということはどういった意味があるのでしょうか?
Y−
私は、全く誰にも見せない作品というのもあると思うのですね。山の中で自給自足して一人でつくり続ける、とかね。
でも、私自身は人に見せること、見てもらうことがすごく好きです。
自分も過去のさまざまな表現に育てられてきている訳ですよ。自分の肉親の親だけが自分を育てたわけでは決してない。例えば、大好きな小説や美術やマンガ、新聞のちょっとしたエッセイまで、
自分の名前を世間に公表して表現を行う人全ての、勇気ある行動に影響を受け、成長させられてきたと思うのです。
だから、作品に対してどんなにとんちんかんな意見を持たれることがあっても、それはそれで良いのではないでしょうか。
そもそも、他人との関係は誤解やすれ違いで成り立っているわけで、なかなか理解はしあえないし、納得できない存在であることから始まります。そして、それが他人の価値なのですから。
むしろ、そういう人達に見せるということは、いいことだと思う。
T−
ご自身の作品が、いつかどこかで他人に刺激を与えられればと期待する部分もあるのですか?
Y−
それは、あるかもしれないですね。作品を見た人に刺激を与えているかもしれないし、
共感を生んでいるかもしれないし、すごく嫌な気分にさせているかもしれない。でも、それはもう作品がひとり歩きをしてしまっているところだから、私には知ることができないです。
つくり続けることに関して言えば、ものをつくることは自分の中を探ることに尽きるのではないでしょうか。自分の中にある井戸を掘るしかない。そして、その井戸は自分の中に何個もあるわけではなくて、大抵1個か2個しかない。それを掘って、掘って、無くなってしまってもまだ掘ってつくり続けること、それしかない。これは、私だけの感覚ではないと思います。
それだけ自分の人生かけてつくっているので、発表する条件や場所も、こちら側からも選び続けていく作業がとても重要です。
T−
「選びとる」ことは、実はとても難しい作業ではないかと思います。
お話を伺っていて、「もてるものが、いいものをつくる」という構造だけに、アートの魅力が集約されないのは、作家が個人として誰を、何を「選びとってきたか」に尽きるのだと感じました。
今日はありがとうございました。
|
|
|

|