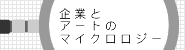
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
YM−
いえいえ、私はもともと販売の仕事がしたくて26年前に縁あって入社しました。最初は食器の販売にいて、次にアートフラワーの部門に異動になりました。やがてその店舗がヒルトンホテル建設の際に立ち退きになったのを機に約20年前に今のダイフィット部門に異動してきました。
T−
あまりにも違うことを求められるお仕事への転向に、抵抗感はなかったのでしょうか?
YM−
それはもちろんありました。アクリルで何をするか全く分からなかったですし、戸惑いは大きかったです。私は本当に不器用で、小さい頃もプラモデルを作り上げたこともないような人間でしたからね。転向になる前に当時の社長つまり今の会長に「私には、技術職は向いていないと思います」とお伝えしたぐらいです。
T−
ことばで伝えられてできるお仕事ではないと思うので、そのとまどいは当然ですよね。
ところで、島川さんは、写真への興味などが入社のきっかけだったのでしょうか?
S−
私も写真や加工についての知識が全くない中で、6年前に今の職につきました。私が担当する営業は、ラボや作家の先生の意向を製作の山口たちに伝えるのが主な仕事です。今は技術的に求められるレベルがどんどん上がっているので、作家の先生たちに直接工場に来てもらい作業の工程を見てもらえるようにするのも大切な仕事のひとつになってきています。
T−
やなぎさんは、モリヤさんとやり取りを始めた頃から、何度も工場に足を運んだことがコミュニケーションを図る上でとても重要だったと言っておられました。 やなぎさんは特に足繁く通われる方なのでしょうか?
S、YM−
おそらく他の作家の方と比べても一番通っておられますね。
S−
企業の営利を考えれば、ラボさんを通すことで幅広い層のお客さんにモリヤを利用していただけるようになるという大きなメリットがあります。でも、アート作品の場合は加工する際に細かなやり取りが必要となりますし、作家の先生にしても製作の顔が見えないというのは不安が大きいと思います。
特にやなぎさんの写真に行うのは、写真の表面にアクリルをフィットする加工です。この技術がある程度の大きなサイズでアート作品として多用していただくようになったのは、やなぎさんが初めてでした。ですから、先生の求めておられるクオリティーを表現することは私達自身にとっても挑戦であったと言えます。
T−
やなぎさんの作品を扱うようになって、何か変化したことはあるのでしょうか?
|

| | |
S−
私はまず、これまで写真家をアマチュア写真の延長程度にしか考えていなかったので、それがいかに甘い認識なのかを思い知らされました。
逆に、入社して日の浅いうちにお会いできたのはラッキーだったと思います。通常、私達はラボの営業さんを介して作家の方の意向を伺うことが多いのですが、アート作品に関してはコマーシャルなものと違い、単に加工して渡せばよいというものではないので直接やり取りさせてもらい製作の持っているアイデアを上手く伝えられる関係にもっとなっていかないといけないと感じていますね。
YM−
うちが取り扱う商品の多くは広告物の加工です。これはまず予算ありきの中で短期間で数をこなすことが最も求められる仕事ですから、「ミスがない」ように気を配りつつもアート作品ほど気を遣うことがありません。一方でアート作品は、美術館などに展示されてその写真を見たいために来る人を相手にしていくわけですから、やりがいが違いますよね。
どんどん技術的な要請をしてもらわないと、仕事をこなすというだけでは私達も新しいアイデアを生み出すことができません。
実は、一般的に加工の仕事は少し煮詰まり気味というところがあります。貼るという基本から枝分かれした技術を究めているわけですが、もっと平面以外のものにも貼ることができるのでは無いかと可能性を模索するようになりました。
S−
企業の持つアートスペースや小さなギャラリーさんに搬入する機会も増えてきたのですが、みなさん熱心に細かいことまで質問なさるんですね。今はラミネートやアクリルパネルが普及してきたとは言え、交通広告などを扱う方以外は、存外珍しい技術なのだと知るようになりました。だから、アート作品を扱う方々にももっとこの技術を知っていただいて、美術館に飾るような大きなものだけがアートではないとするならば、手軽に持ち歩いたり、プレゼントをしたりできるレベルに作品を加工したりもできないのだろうかと考えたり。
いずれにせよ私たちはどうしても受け手側というポジションにいるので、アート作品を扱うこと、作家の方とお話することで新しいアイデアのヒントをもらえると感じます。もっと企業の技術力を活かして、アートを支援しつつ関わることができればと思いますね。
T−
個人としてはどのように作品を受け止めておられるのでしょうか?
YM−
私どもは、モリヤがあってやなぎ先生とも知り合えたわけですから全く仕事を離れて、作品について話すというのは難しいですね。
でも、『エレベーターガール』から関わらせてもらっていますが、最初に見た時はこれまで自分が知っていた写真作品との違いに「なんやこれは!」と驚きました。やなぎ先生の作品は合成を使っていますよね。いつも見なれた梅田の阪急百貨店のアーケードというのは分かるけど、どうも違う場所に見える。不思議でした。広告以外では、風景を写したものが8〜9割で、写真の善し悪しよりも見ていてきれいやなあという感想をもつことはよくあるのですが、それとは、ちょっと違う感覚を覚えました。そういう感性が動かされるようなものを、今一緒に働いている若い社員にも見せてあげたいと思いますね。
S−
僕は作品に興味が湧くのが楽しいと感じています。それは、人に対する興味が湧いて、やる気が起るのと同じことではないでしょうか。山口が言うように、営業の人間に比べて製作の現場では、なかなか自分達が扱ったものの最終結果を見る機会がありません。そこを営業が埋めていかなくてはならないのですが、できればみんなのモチベーションをあげるためにも新しい仕事や作家の方々の新しい感性に直接出会ってほしいと思いますね。
営業としては、利益率の良い仕事つまりは広告関連の発注をどんどん引っ張ってくることも大切なのですが、利益率は数段落ちても、作家の先生との関わりは口をはさめるといってはなんですが、アイデアを交換できる可能性があります。それは私自身にとっても大きなモチベーションになりますし、企業としてのモチベーションのアップに繋がると感じます。
YM−
どうしても加工をしている時は、作品よりも商品としての意味合いが強いから、横に倒した一定の角度から蛍光灯の光で近視眼的に見るしかないのですね。でも、実際に展示される時には違う条件で見られるわけですから、どこから光を当てた方が美しく見えるのかを先方にも伝えられるようになりたいし、私達もお客さんの要望に叶っているのかを細かく知りたいと思います。
T−
工場を拝見させていただいた際、若い社員さんも多くおられましたが、今、山口さんおっしゃったようなお考えやノウハウを全て伝えていかれるのは難しいのではないでしょうか?
|

| | |
YM−
企業としての技術力を保ち続けるというのは、実はとても難しい。なんせ一人ひとりの手にかかっている部分がほとんどですから。新入社員を迎える前には面接も行うのですが、話しだけでは分からない動きがものを言う仕事です。今、工場にはみっちり間を繋いでくれるような30代の中堅がいなくて少し困っているというのもありますね。
加工のミスをしないには、なんの仕事もそうだとは思いますが「言われたことはできるけど、それ以上のことはしない」のでは周りの動きと上手く噛み合うことができない。逆に、それができる人は覚えも早く、みんなを引っ張っていく力を発揮してくれているように感じます。
S−
私達の仕事では「創造性」というのはつくる前の問題であって、つくりはじめてからはいかにミスをしないかが重要です。先程、山口は自分にはこの仕事が向かないと考えていたと言いましたが、私はむしろその逆だと思います。もちろん私から見れば十分に器用。そして、それ以上に「ミスをしない」というクオリティーを守るために、ミスを避ける準備が十分にできる人だから今の立場にあるのだと思います。
T−
なるほど、アーティストと技術者のパートナーシップも重要ですが、製作と営業のコミュニケーションもとても大切ですね。さまざまな視点が刺激しあうことで、新しい技術へのヒントが生まれてくるということをお二人から伺えたように思います。本日は長時間ありがとうございました。
|
|
|

|