|
|
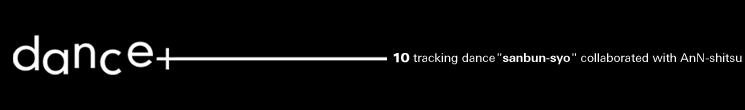 |
| AnN-shitsu presents シキのコンクリート《散文抄》 2005年11月05日-06日
築港赤レンガ倉庫315
|
|||
作品レビュー《散文抄》#02
こういったやり方で親密なコミュニケーションを生みだした第1部に対して、第2部は対照的なやり方で、また観客にはたらきかける。まずソロと2組ごとのデュオで構成もわかりやすかった第1部に対して、4人の即興が同時進行する第2部は、空間や時間の始まりや終わりが曖昧だ。白から黒への衣替えは、光の少ない空間にダンサーの輪郭を溶け込ませる。ムジカ・イーゼルの演奏は、なんと言ったらいいのか、フレーズや音が知らない内に始まったり消えたりしており、けれどもたしかにそこに在る。そうしてそれぞれ異なる筋道を持つダンスが空間のあちこちに散らばって、視線の焦点を分散する。 こんな風に踊りに目をうばわれつつ焦点が解放されると、いろんなことが起こる。ここからちょっと怪しげな感想になってしまうが、まず空間のあちこちが溶け出したみたいになる。そして、自分が見ている位置や角度にとらわれずに見るようになる。挙げ句に、自分のと同様、ほかの観客の視線も空間に漂い出しているような気配を感じる。ダンサーがそこにいてわたしがここにいるといった、日常で頼みとしている時空間にもとづく位置関係や距離感は、そこではいかにも心許ない。 注意を払うべきものがあまりにありすぎて、自分がその中でうまく運動できているとき、-例えば集団スポーツのゲームで-、自分を取り巻くフィールド全体が360度一挙に克明な像を結ぶといった感覚に襲われることがあったけれど、そういったこともちらっと思い返される。おそらく、意識の領域で働いている世界の秩序みたいなものが効かなくなってくるのだろう。それを理性に対する他者の発現とかいうなら、そこで夢だの、忘れられてきた記憶だの、何が現れ出てもおかしくない。芸術は、こういった意味で解放の場であるとよく言われる。面白いのは、その体験を言葉にしようとするとき、言葉の論理が一人歩きして物語をねつ造しようとするのに対し、身体がそれに抵抗することだ。 |
|||
これに似たような葛藤が、『散文抄』でも見る者の中に引き起こされたかも知れない。たとえば、チラシに書かれた「かつて、恋にしか罹らない病が流行し、大量の恋が死んでいった…」というフレーズから予感される恋愛歎を、ダンスに読みとろうとするとき、それはどうにも無理っぽいのだった(実際は「物語」ではなく「詩」なのだけれど)。確かにダンサーたちは、男と女という記号性を辛うじて備えてはいた。ところが、その所作や相互のやりとりに、わたしたちが経験的に知る人間関係の機微が一瞬浮かび上がるように思えても、それによって指し示されたものが頭の中で物語として展開することはない。ダンスによって、見る者の意識は指し示しているものそのものに常に引き戻され、また4人の関係が織りなす意味や筋道を「読む」といった構えが効かなくなっていたからだ。だからそこで展開するものは、すでに語られてきた物語に沿わないだけでなく、始め-中-終わりのあるような「物語」という次元をそもそも持たないのだ。 こんな風に考えてくると、『散文抄』の体験を反芻する手がかりとして最もふさわしいテクストは、チラシをひっくり返してみると一番下にそっと書かれてある「物語は物語られずとも人は持っている。」なのかも知れない。この「物語られ」ぬ物語の種を秘めるいくつもの身体が、ダンスに誘われ口を開きだす。あの日の赤レンガ倉庫の空間では、あちこちでそういったことが起こっていたのではないだろうか。 text by メガネ(log osaka) photograph by 井上嘉和 |
|||
< back |
next
> |
||
| Copyright©
log All Right Reserved. |
|||