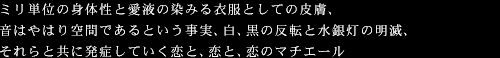
散文抄は、なぜ散文抄でなければならなかったのか?
恋は、なぜ悲しみと結びつく想いでなければならなかったのか?
奇病は、なぜ死に向かう生でなければならなかったのか? いずれにせよ、この奇病は死に至るほどの難病なのだ。致死量に達してもなおも皮膚に纏わりのたうち廻るほどに狂わせ、悲しみの同心円を深々と色濃く刻みつける。しかも厄介な事に、この病は伝染する。想いが募れば募るほどに、悪化する症状が向かう思考思想は死のみだ。純粋な身体を持つ彼、彼女らが「死」の発見の後で「性」に目覚めるのは因果か。いや、それを運命などと言ってのけても溢れ出る泪を否定できない。沸き立つ感情、背徳、淫蕩、抑圧、そして、みな「恋にしか罹らない病」に感染していった。
焦燥、静謐なる緊張、または倦怠。いや、高揚感が募る。赤銅色の扉が醸す錆び付き甘い空気が立ち篭める。この倉庫にいるのは何日目だろうか。バックステージ。ここは静かだ。机に鏡を置いただけの壁も扉もない簡易のメイクルームに出演者は集まっていた。オレンジ色の光に釣られたバタフライのような息を潜めた可憐だった。客席から騒めきが聞こえだす。昨日よりはおとなしいか。そうして、我々はどこの銘柄とも知らぬ赤のワインを、例に倣って血として混じ合わせ掲げる。
「かつてあった大量の恋の死という現象を、トラウマよりエクスタシー な美の芳香で満たそうではないか!
エレンガント且つロマンティシズムな病を発狂寸前まで発熱させるパレードを!」
我々は祝杯をあげる。
祭壇に向かう表現者を眺めながら、
私は若き詩人と皇女の事を考えていた。
あの恋もやはり悲しみと共に死に向かうのだろうか、と。
飲み干したワインが詩人の血と知として身体を巡っていくのを感じて。

「恋」を表現できるのか
その目で確かめればいい
その肌で何度も触れればいい
耳を塞いでも確かに聞こえてきたでしょう
どこか分からない場所が熱くなったでしょう
それで充分なはず。
哀しくて苦しいでしょ
切なくて憎いでしょ
いっそ、いなければと想像したでしょ
けれど求めるのでしょう
それでいい。
感情が揺れる
その変化を忘れないでいればいい。
「それよりも知りたいのは、如何なる時に彼女が宝石よりも美しいあの微笑を見せるのか…」
夕陽が眼を刺す。これは全くの虚構の夜だ。
それでも、詩人は旅をする。シキのコンクリートを…
「物語は物語れずとも人は持っている。これは人の持つ物語の空気に触れる虚構の散文。」
text by fuca(AnN-shitsu) photograph by 辰巳千恵 |

