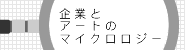
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
「骨のある表現者を見つけたい」− アリス零番舘 -IST
芸術監督 佐藤香聲 さん(Satoh Kashow)
所在地:アリス零番舘 -IST 大阪市中央区南船場1-16-2 ふぁみーゆ南船場B1
tel:06-6261-2876
1960年 姫路生まれ。小学生から古賀政男のギターに親しみ、高校生の時には、ロックバンドでギターとキーボードを担当。
1988年 楽曲を視覚化する演劇的コラボレーション集団【銀幕遊學◎レプリカント】を大阪で結成。
代表・台本・楽曲・舞台効果・演出を担当する。
2004年 【アリス零番舘 -IST】芸術監督に就任
銀幕遊學◎レプリカント(*1/以下レプリカント)は音楽を視覚化することを試みる。アーティスティックな衣装とメイクを施したパフォーマーによる身体表現とライブ演奏を中心とした、ビジュアルとサウンド基調のステージづくりを行う。 フリースペースを始め、美術館や能舞台、寺の本堂と境内、また欧米やアジアなど海外でも作品を発表し続けている。
佐藤さんは「アリス零番舘 -IST」の芸術監督、レプリカントでの活動、そして広告宣伝のプランナーやディレクターなどさまざまな顔を持つ。
|

| | |
辻(以下[T])−このたびは[-IST]のご開幕おめでとうございます。
佐藤(以下[S])−いやいや、なんとか開きました。
T−
まずは、[-IST]を立ち上げることとなったいきさつを伺えますか?
S−
「アリス零番舘 -IST」は劇場の名前の一部ともなっている東京新宿の「タイニイアリス」という小劇場のオーナー西村博子先生と、レプリカントの女優である栃村結貴子によって共同経営されています。
西村先生は近現代演劇の研究者でもあり批評家でもありますが、20年以上経営する「タイニイアリス」を通じてさまざまな劇団を巣立たせてこられた方です。例えば東京の劇団では新宿梁山泊や三宅佑司のスーパーエキセントリックシアター、劇団三〇〇、劇団青い鳥など、名古屋の少年王者館、大阪の南河内万歳一座など。彼らが若い頃はみんな、タイニイアリスを通過していったわけです。まあ、西村先生本人は巣立たせたと言っていますが、当時の小劇場と言えばタイニイアリスしかなかったんでしょう!!
T−
「そこしかなかった」を強調されますね。
S−
新宿には猥雑な雰囲気がありますからね。60年代には唐十郎の赤テントが神社に立っていたり、寺山修司や蜷川幸雄らが公演した映画館とかあったそうで、若者を挑発する街のエネルギーにあふれていたんでしょうね。
T−
わざわざ東京の方が劇場設立に動かれたのですか?
S−
タイニイアリスが毎年行う「アリスフェスティバル」という、全国から劇団が集う公演に出演させてもらって以来、西村先生とは「アリスのように若手の登竜門と成っていくような劇場を関西でも作れたら」とずっと話していました。それで「どこか直感できる場所はないか」と探しはじめていたんです。もちろん、僕たちも僕たちで関西は土地柄か芸達者、エンターテイメント性に溢れた表現者はたくさんいるけれども、そういうのではない表現者が使えるような場所が欲しかった。そんなに観客は呼べないけど、演劇に熱を入れてる劇団がね。そうして話が合致して3、4年前から準備を始めていたんですわ。
T−
そんなに前から探し続けておられたのですね。
S−
ええ。で、2年前に話しがまとまりかけたんですが資金面でのめどがつかず、一旦とん挫して。それでも、「なんとか実現したい」と探し続けていたら今の場所(南船場)がみつかり、めでたく開幕という運びになりました。
T−
若手の登竜門にしたいと考えたのは?
S−
僕は「銀幕遊學◎レプリカント」という実験的なパフォーマンス集団を率いていますが、先駆的なことをやっている劇団がもっと活動しやすくなればとの思いが強かったです。
でも、最近周りを見回すと、どうもそうした劇団や俳優が少なくなったなあと感じています。若手の劇団に「あなたたちの目標はなんですか」と聞いたら、「観客の数を増やすことです」と答えるようになってしまっているんですね。 要は、劇場サイドがあまりにもシステマチックになってしまい、劇団の評価の基準が観客動員数に重きを置くようになったのか、劇団サイドもその基準に引っ張られているのではないでしょうか?
T−
観客が増えることを表現の結果としてではなく、目的そのものとして捉えてしまっているということですね。
S−
公演は興業の一面が強いですから、観客の動員自体はそれとして大切なこと。でもあまりにもそこにこだわることに違和感を感じざるを得ないんです。この状態はまずいなぁと。
西村先生のことばを借りていえば、「近現代演劇史の中にちゃんと位置づけられる」劇団を見つけて、若手を育てられる場を関西にもつくるべきと考えたんです。
T−
今の演劇シーンはこの人たちが作っていると納得できるような質的強度をもった表現を巣立たせていきたいとの思いがあるわけですね。
S−
芸術監督としては定期的に行う演劇祭には、あまりマスコミの言動に踊らされない、骨太な現者を見つけて行こうと考えています。カラーを揃えていこうと。
T−
そのカラーというのは?
S−
劇場を探す時の第一条件が「地下にあること」だったんです。そう、カラーは文字どおりアングラ(アンダーグラウンド)ですね。といっても別に俳優がみんな白塗りの顔をして、おどろおどろしい雰囲気を作るというわけではないですよ。
今回の10月−12月のオープニングラインナップにしてもアングラという軸ではそろえていますが、それはあくまでも精神的なものであって。アングラの精神は「創造の情熱=破壊の情熱」でしょう。それさえあれば、実験的な作品、エンターテインメント志向の劇団、コントのようなお芝居と、ジャンルは問わずに選んだつもりです。
|
|
|

|