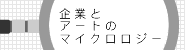
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
T−
劇場を作ること=佐藤さんのこれまで表現者としての経験値、小劇場演劇が行ってきた歴史が試される連続だったと言ってよろしいのでしょうか。
S−
レプリカントは、もともと演劇が近代化する中で、「ジャンル」として分けられてきた要素、つまり「セリフ」「身体表現」「映像」「演奏」などをむしろ積極的にミックスした表現を試みて来ました。それで、ふつうの舞台におさまらないことが多かったのですね。結成当時、いろんな小劇場スペースに公演企画をもちこんでも断られる連続。「こんなのは小劇場演劇とちゃう!」って。それでも、今や老舗のライブハウス「FANDANGO」の支配人などはおもしろがってくれて、よく使わせてもらいました。
だから[-IST]ではできるだけいろんな劇団が、思う通りの舞台をつくることができるような場所にしたいわけです。これまで自分がやってきて不便だったり、こうなればと思ったことをできるだけクリアしつつ、フレキシブルな使い方ができる自由度をもたせたかった。
どこからでも照明を操作できるようにしたり、動かせる舞台にしたのは全てそのためです。
先日のこけら落とし儀式に[-IST]で公演が決まっている劇団のほとんどが来てくれたのですが、それぞれの劇団が「ぼくのところはこっちを舞台にしたい」「この客席をこっちとあっちに分けて置きたい」とか言ってきてくれましたね。それを聞いているのが、とても楽しい。
T−
佐藤さんのシュミレーションを上回るような未来の表現者がでてくるのか?まだ見ぬ表現と勝負をされているようです。
S−
それは本当にそうですよ。まだまだ「若い才能を発掘して!」という西村博子先生の要望に応えている場合じゃないですよね。
T−これまで表現者として劇場を使う立場だったのが、劇場を使ってもらう側になっての発見などは?
S−
10月2、3日にはじめて「南船北馬一団」という劇団のメンバーとジョイント公演を打ちましたが、やっぱり作り方が全然ちがうなあと改めて感じました。
細かいことなんですが、場当たり(テクニカルなリハーサル)の仕方や、立ち稽古の順番が微妙に違ったりするのを肌で感じましたね。
T−
劇団によってもっているスタイルや方法論が全く違うことに「劇場側」として初めて気付いたと。
S−
ということは、今後もずっとこの違いにつきあっていくのは大変、と正直に思いました。
T−
おそらく稽古の付け方というのは、人の呼吸と同じくらいに身体化されたものじゃないですか。だから、それぞれの呼吸法というのはそれほど違っていて、大切なものだと思います。
S−
カラーが出始めたり、作風が安定してきた劇団にはより強くこの違いを感じます。
それぞれの劇団にとって、心地いい状態をつくってあげられるようにしてあげられればと思いますね。
[-IST]を立ちあげるにあたって、一番に考えたことは自分達がイヤだと感じたことは他の劇団が味わうことがないようにしようというものでした。
レプリカントをやっていていつも感じていたのが、劇場の「時間的制約」をもっとフレキシブルにできないかということ。どこの劇団も貧乏ですから、経費を安くするために劇場を一日でも、数時間でも少なく借りなければならない。だから劇場入ったとたん時間との戦いですよね。仕込み(セットを立ち上げるなどの作業)して、リハーサルして、本番して、撤収してと。
何度となく、本番の前の日には「あと30分あれば、もう1シーン、リハーサルできるから、閉館を少し遅くしてくれないものか」と悔しい思いをすることがありました。
だから、[-IST]では23時閉館と決まっているのですが、その決まりもあってないようなものにしてます。夜通しの仕込み、朝までリハーサルも。
あとは、いろんな劇団が無茶をしてくれて、僕たちの予想をどんどん上回っていってもらいたいですね。
T−
それは劇団にとっては嬉しいことでしょうが、劇場側にはかなりの体力が必要ですね。
S−
公共の施設とかになると、閉館時間が迫ると舞台の担当の方なんかが周りをウロウロして片付け始めたりする光景があるんですよ。「そろそろ終わりにしぃやぁ」って顔で。それで劇団サイドはそこで創造のエネルギーを中断せざるを得ない。だから[-IST]は事務所を劇場の中に置くのではなく、外に置いています。集中してつくってもらえるように。
しかし、もうすでに弊害がでてます。時間に制約がないとダラダラする輩が…、それは僕かも。「まだ時間があるし、気分転換にラーメンでも」とかになってしまうんですよ。
T−
レプリカントは、[-IST]を拠点にするのですか?
S−
事実上レプリカントの拠点にはなっていくとは思いますが、もちろん会場費を払いますので、もっと安く使わせてもらえる劇場があれば、どこにでも行きます!
というよりも、どこか特定の劇団の拠点というイメージを作りたくはないんです。「人の家で食う飯ほどまずいもんはない」のと一緒で、ある劇団だけのカラーがつきすぎた場所の合間をぬって公演するのは、ほかの劇団にとっては心地いいものじゃないでしょう。やっぱりどこに劇団にも「今は自分たちだけの劇場」と実感してもらいたいですから。
T−
初めにおっしゃっていたアングラの精神を考えたら、「居着く」というのは似つかわしくないということですね。でも、アングラを謳う想いは、なかなか一般的には理解されないのではないでしょうか?例えばご近所さんとか。
|

| | |
S−
そうですね、スタイルよりも勧善懲悪型のお話でないことを理解してもらうことは難しいです。でも、美術展示の時なんかは劇場前の喫茶店のウェイトレスさんとか来てくれてますよ。その喫茶店のママさんは店にチラシを置いてくれたり、近所のにお好み焼屋さんはチケットをさばいてくれたり、「船場村」というネットワークの村長も口コミで宣伝してくれたりと、少しずつ街の劇場に成長していけそうな気配が感じられてきました。
T−
環境が大きく変化していると思いますが、今後やりたいことは何ですか?
S−
そうですね、今はオープニングフェスティバルをとにかく無事に終わらせたいと思っています。それで振り返ってみて、問題があると感じられたことに関しては早急に対処していきたいですね。次の劇団が使う時に、同じ問題をもちこさないようにしたいです。
T−
まだまだ大変な時期がつづくこととは思いますが、ぜひともがんばってください。近々、関西圏でも意外と知られていない和歌山の劇団なども登場予定ですよね、楽しみにしています。
*1銀幕遊學◎レプリカント http://www.geocities.co.jp/Hollywood/3332/
|
|
|

|