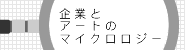
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|

| | |
T−
なんだか、もの凄く壮絶ですね。
I−
でもね、芝居ってこれぐらい現実の世界と実際に生きている自分との間にあるギャップを経験せんと、本当に面白いものはできへんとちがうのかな。それに、僕らの時はそれぞれの仕事の領分なんて決まってなかったから、裏方がよく、芝居に口を出してましたわ。だから、1つ芝居つくるのにすごく時間がかかった。飲み代は一杯かかったね。芝居をやっている時間よりもそうやって飲んでいる時間の方が長かったりしてね。
今の芝居の課題は、もしかしたらそこらへんにあるのかも。作る者がどういったリアリティーをもち合せているかというね。
T−
お客さんの方も、おっしゃるような壮絶なリアリティーは持ち合せていないと思いますが。
I−
そうでしょう。だから舞台とお客の関係もなんか希薄というかね。
実はね、[-IST]の客席を作る際に、僕はもっと客を詰めて座らせたほうがいいと提案したんですわ。[-IST]の二人はせいぜい100人しか入らないというから、あそこやったら200人は入るって押したんですわ。
T−
先日70人ぐらいの観客の中に座りましたが、少しきついかなと感じましたよ。ぐっと身体を傾けたりすると、隣の人の腕や後ろの人の足に当ったりしました。それぐらいがいいということですか?
I−
そう!あの寸法はよくよく考えた寸法です。あれ以上狭いと座りにくすぎるし、広いと舞台が狭まってしまうぎりぎりのせめぎあいの寸法なんですわ。
T−
大人しく座っていると周りの観客に当ることは無いのですが、だんだん芝居や音楽に乗ってきてからだが動きだすと隣の人に触れる感じでした。逆にいえば、周りの観客が乗ってくると、こちらも自然と乗せられていくような気がします。
I−
まだまだあれは余裕があるじゃないですか。極端に言ったら「動けんぐらいにせい」と思うわけです。芝居をやっている方もしんどいんやから、見てる方もちょっとはがまんせい、とね。ゆったりと座ると、余計なことを考える余裕が出る。いかに舞台に集中するかが舞台と客の関係ですよ。演じている方にとっては、舞台のことが現実じゃないですか。せめて数時間ぐらい、眼の前の現実のせめぎ合いをどう一緒に体験するかが「芝居を観る」という行為なんじゃないのでしょうか。
まあ、これにはいろいろ議論があると思うけど僕の持論やね。どちらがいいかの判断は各自のものだと思いますが、少なくとも「アングラ」で突出した劇場にしたいと考えるのであれば、こうやって集中する空間というのが外せないと思いますね。両方のアドレナリンを混ぜ合わさないと!
T−
現在、職を変わられてからも演劇に対する思いは、形を変えて深まっておられるように思います。同世代の方と演劇についてお話をされる機会というのはよくありますか?
I−
うーん、あんまりないね。でも僕はおもしろそうな芝居があったりすると、同業の人にも声かけてるわ。「どうや、こんなんあるけど行かへんかぁ」ってね。
T−
木工業界に密かな演劇ネットワークができる日も近い?
I−
できたらええなあと思うとんやけど。まだまだやね。
[-IST]を実際に立ち上げると聞いた時は心底、大丈夫かと思ったから、できることは手伝ってあげれたらと思う。でも、僕も演劇を離れてから長いから、どうやれば劇場が上手くやっていけるかとかは、具体的にはもう分からない。だからこそ[-IST]みたいな劇場があって、そこにちょこちょこと足を運んでおれば、また面白い芝居に会えるという状況があればいいなと思うよ。
T−
今日は、本当に長い間ありがとうございました。また[-IST]公演観劇の際、お会いできればと思います。
* 2 初日の直前に本番と全く同じ手順で行う稽古のこと
●おまけ
今回はどちらも長文となってしまいました。熱き演劇人の長時間語っても尽きぬ深みに引き込まれてしまいました。
「アングラ」がはっきりとひとつの潮流を築いていた時代。それをリアルタイムでは知らない私にとっては、竹内さんの熱っぽさから佐藤さんのバランス感覚に至る流れこそが、アングラの流れそのものを肌で感じることのできる実際でした。
奇しくも、インタビュー中にお二人から出た同じことば−「あらゆるシチュエーションを想定する」ことは、経験と時間を積み重ねて初めて手に入れられるものです。竹内さんがおっしゃるように、この気の遠くなるような作業を身体化していることが「プロ」の証拠なのだとしたら、竹内さんはもちろん、佐藤さんも「プロ」です。ただし、お二方を何のプロかと名付けることは私にはできないと感じました。
なぜなら、お二方とも職業というカテゴリーでくくるには、あまりにも別の側面が輝いていて一面的な「○○のプロ」ではないように感じざるを得ないからです。もしかすると、悩んだり、間違えたり、冒険してみたりしながらどうにか前に進もうとする生き方のプロなのかもしれません。
そういう大人のいる地下劇場です。劇場があるから表現する作り手を量産することよりも、表現したいものがあった時に自在に変化してくれる場として、[-IST]は「アングラ」や「小劇場」という形なき運動の新しい展開を見せるのではないでしょうか。
|
|
|

|