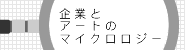
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
T−
先程マスコミに振り回されない劇団ということをおっしゃっていましたが、[-IST]ではその辺をフォローする取り組みは行うのですか。
S−
今は、前宣伝ばかりで作品自体を振り返ってじっくり評価するような媒体が少なすぎますよね。「劇評」が少なすぎるという状態。だから[-IST]では、今数少ないであろう劇批評家の人たちを探し出そうとしています。彼らにうちでやる公演をいくつか見てもらいその中から気に入ったもの、ひっかかったものについて劇評を書いてもらいます。そしてこのオープニングフェスティバルの後、劇評集としてフリーペーパーにして配布しようと考えているわけです。
T−
表現者でもある佐藤さん自身にとって、批評はどういう存在だったのですか。
S−
実際、タイニイアリスはずっと、こうした批評活動の支援も行ってきてたんですよ。西村先生曰く、劇評がないから作者に「見た人」が与える影響が薄まって、演劇と社会もつながりにくくなってきていると。僕もタイニイアリスで上演した際には、作品について「ぴしっ」と書かれたものを読むことで、創作の新しいヒントを得てきたわけです。作品のいい点も、疑問点も書かれていると「ああ、そう言うふうに発見してもらえた」「こういう取り違えもでてきた」とね。
[-IST]でこの取り組みをするにあたって、西村先生がおっしゃられたことが1つあります。「この劇団にくっついておけば、将来食べるのにも困らない」とべったりくっつくような批評家は連れてこなくてもいいということでした。それは、東京で彼女が感じている問題なんでしょうね。要するに、劇評を書かしてもらえるから、この劇団と仲良くしておこうというような輩が多すぎるという変な状況がね。
T−
おかしな依存関係でなく、互いが自立した関係でいるべきだと。でも関西で食いっぱぐれない補償のある劇団はほとんど見当たらないように思いますけどね。
S−
そう、ないですし、書く機会もほとんどないですから。
T−
劇評は、なまの公演を見ている時とはちがう、舞台と観客のキャッチボールが生むひとつの手立てだと思います。そこにはある程度の見た人の層とオンタイムさがあって生きてくるものではないでしょうか。だから出版関係のほとんどが東京にある現状いおいて、[-IST]として取り組まれる意義は大きいと感じます。ところで、こうしてソフト面の充実化に手をつける以前、劇場のハード面の準備はどうなさったのですか。
S−
[-IST]の場所はもともとマージャン屋さんとして使われていたところらしいんですが、初めに取り組んだのは「防音の問題」でした。音が周りにもれてクレームが来てしまうと元も子もないので、大音量を出してみる実験をしました。実際には、ドラムやキーボードなどを持ち込んで、平日と休日の2日、ロックの生演奏をする位でも大丈夫かどうかをドンドコやりました。
|

| | |
T−
レプリカントも音楽を多用したパフォーマンスをされますからね。
S−
それで周りの事務所やお店の方にもいろいろ音の影響を聞いて回ったのですが、「ちょっと聞こえるけど気にならへんで」とみなさんが言ってくれるのを確認できました。南船場という土地柄、FMラジオを聞きながら仕事をしているような、そんなにお堅くない事務所がほとんどだったので安心しました。
T−
他にも、作品をつくる際とはまた違う方々との関わりを模索しなくてはならなかったのではないですか?
S−
そうですね。 ふつうの家や事務所を設える感覚とは全く違うわけなので、施工をしてくれる業者さんには何度も説明をする必要がありました。
例えば電気工さんに電気のスイッチを手を上に延ばしたら届くぐらいの高さに付けてくれと頼んだら、びっくりされました。「背の低い子が困るやないか」とね。でも、以前レプリカントの公演の際に、俳優のひとりが舞台袖にあったスイッチにふいに肩を当ててしまい、会場の蛍光灯が一斉についてしまったというハプニングを経験したことがありました。だから、絶対にスイッチは簡単に触れない場所にしようと決めていたんです。とにかく、通常の工事や施工とは違うことをしてもらう連続で、業者さんを困らせました。けれども最後はよく理解してくれたように思います。こちらが知らない法規関係についても教えてくれたのがありがたかった。
T−
配線関係は一度つくってしまうと、簡単にかえられる部分ではないですからね。他にも劇場では客席と舞台の位置などが、作品を見せる上でとても重要になると思います。舞台はどのようにしてつくられたのですか?
S−
舞台と客席は「いちい工芸」さんにお願いしました。舞台や客席のひな壇も全部取り外しができるように考えてもらったんですよ。僕たちもあらゆるところを舞台にできるように、あらゆるシュチェーションを想定しましたね。かつて小劇場演劇のメッカ的存在だった「扇町ミュージアムスクエア」ではあらゆる場所が舞台にできて、レプリカントの公演では会場のセンターを舞台にして観客がそれを取り囲むとか、会場に入ったらそこが舞台上だったとか、いろいろ無茶させてもらいました。その度にデメリットも経験しましたが、結局はそういう挑戦や経験ができて今の創作活動に繋がってると思います。
T-
いちい工芸さんにお願いされたいきさつは?
S−
いちい工芸さんとは、オーナーのひとりの栃村の実家が古くからの知り合いだったそうです。なんと、今の代表が大学時代に東京で演劇をやっていた経歴もあり、話が通りやすかったですね。彼が所属していたのは「劇団 摩呵摩呵」というアングラ劇団で寺山修司の実験映画に出演したりしていて、後に「ブリキの自発団」に改名し、片桐はいりや銀粉蝶らの奇妙キテレツな女優を輩出しています。
T−
じゃあ、いちい工芸でなくてはできなかったと感じられることがあったのでは?
S−
もちろん演劇を知らない業者の方に、ひとつひとつ説明し、完成を確認することは僕たちとしても勉強になった部分が大きかったです。でも、やっぱり、小劇場演劇の経験者ということで、断然に段取りがよかった。
劇場のキャパを算出してもらい、そこから桟敷席とひな壇の客席数を考案してもらい、それにもとづいて、ひな壇の段数や幅、高さを計算して、作ってもらいました。
ミーティングの時に、いちい工芸さんが「昔と変わってないなあ」と何度もおっしゃってましたが、小劇場演劇の現場というのは、30年経っても、まったく変わっていないという現状が浮き彫りに。これって、いいこと?もしかしたら、まったく進歩がないってこと?
|
|
|

|