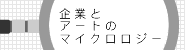
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
「概念を現実に落し込む作業」−有限会社いちい工芸
代表取締役 竹内哲児 さん(tetsuji takeuchi)
|

| | |
所在地:大阪府松原市別所6-2-19
1940年 大阪府住吉区生まれ
1953年 父親忠さんが木材工芸社を創業
1973年 いちい工芸に社名を変更
1979年 哲児さんが代表者に
1988年 有限会社いちい工芸に
公共施設、オフィス、個人住宅の別注家具の設計、制作、造作を行う。図書館、病院、学校をはじめ、東急ハンズなどからの注文を受けて、特設の木製家具などを製造する。日比野克彦氏デザインの家具をコラボレーション制作されたこともあり幅広く手掛ける。
T−
本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。 まずはいちい工芸さんのお仕事について伺えますか。
竹内さん(以下[I])−
うちは、老人ホーム、教育施設などの公共施設、個人宅などに設置する家具の設計や制作をしています。取り引き相手さんによってどこまで手を入れるかは変わりますが、内装デザインから制作まで手掛ける場合もあれば、図面を提案するだけの時もあります。木工にかかわること全般をケースバイケースで行っています。
もともとはおやじが木工業を始めたのですが、簡単にいえばそれを私が後を継いだわけです。
T−
時代に合せてお商売のやり方も変えていかれたのですか?
I−
まあ、そうやね。昔のことはあんまり詳しく分からないけど、おやじの時とはやってることは全く違いますね。 木工業を始めた当初は僕は何も分からんかったからね。自分の知り合いのつてとかを辿って「こんなんやってますからよろしくお願いします」と頼んでね。今は、製造に比重をおいてやってます。
T−
こうした製造は手作りでやっておられるのですか?
I−
この業界で100%手作りでつくっているところはほとんどないね。手作りで全てやっているようだったら、成り立っていませんわ。木材を切るにしても大形の裁断機のコンピューターに切りたい形の情報を入力して製造していますし。でも、業界の中では、うちの業態というのは手作りに近いかな。30−40代の従業員6人程と一緒にやっています。
T−
みなさん、ここで技術を習得されるのですか?学校で習って来れるというものでもないですよね。
I−
へたに学校で習わない方がいいですね。学校で教えていることは間違いではないですけれど、その通りに現場でやられると仕事にならないですから。応用が効かないと現場のスピードや段取りにはついていけないでしょうね。自分で考えられるか、工夫ができるかが、お金をもらって仕事をしているプロ意識なんとちがいますか。
|

| | |
T−
さて、[-IST]の立ちあげに際して、いちい工芸さんが協力なさったことについて伺えますか?
I−
もともと[-IST]の経営者のひとり、栃村さんのおじい様が木工業を営んでおられて、同業種ということでうちとも面識があったんです。面識があってほんとに小さい頃の栃村さんを見ていたから、話を聞いてまさか演劇しているなんて思いもしませんでしたわ。まあそれで、今回の話が突然転がり込んできました。それにしても、まさか、本当にやるとは想像していなかったからなあ。最初に栃村さんから話をきいたのが今年の6月です。どうせ立ち消えになるやろうと思っていたから、8月頃に改めて電話が来た時はびっくりしました。その時はすでに-ISTさん側で話がどんどん具体的になっていって、平台、舞台まわり、客席をつくりました。
T−
いちい工芸さんでは、そうした舞台関係の装置をあつらえたりなどは普段やっておられることではないのですよね。
I−
やっていませんね。今回のような仕事は、お金にもならんので社長の私としては許されへんはずの仕事ですわな。それに、僕ら(木工業の方)が現場で見て「ここはこうやな」と思う感覚と、佐藤さんと栃村さん当事者の二人が考えることに結構大きなズレがあって、それをうめるのに時間をかける必要がありました。
T−ズレというのは?
I−
入口をどこにするのか、人数をどの程度いれる予定なのか、舞台をどっちに設定するねんとか、じゃあ舞台を固定しないならどう作るのだとか、ぼんやりと頭の中で描いていることを、こちらは1個1個現実に落し込んでいかないといけないわけですから。
T−
佐藤さんは、できるだけフレキシブルな場所にしたいと何度もおっしゃっていました。
I−
それは概念的には分かるねんけど、こっちは具体的なものをつくらないといけないので。互いの考えの違いを擦り合わせるために、7、8回図面を描いては見せて、見せては直しという作業をくり返しました。時にはA案、B案と用意していって、選んでもらったり。 その中で、いかに[-IST]の二人がもっている概念的な「フレキシブルに動かせる」場所を体現できるのかを、考え続けましたね。
|
|
|

|