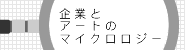
| 小粒のメセナ?個人の趣味?アートを支える多層なアクターに突撃 |
|
|
|
|
T−
私達が普段目にする劇場というのは、基本的な装置は準備されているものなので、なかなかそこからあつらえるという段階を想像しにくいものですね。つい、現場で手直ししてもらえるのではないかと 甘い考えをもってしまいそうです。
|

| | |
I−
いや、それはないね。現場ではどうにもなりません。僕はこの業界ではやっぱりプロなわけだから、そういうことはしたくなかった。それに、ちょこちょこ手直しをすると、かえってお金がかかる。低コストで押さえるためにも、頭の中で案件を全て押さえておかないと。
考えられるかぎりのシチュエーションを想定して、用意できるかどうかがプロとアマの違いでしょう。
T−
なるほど。舞台の基礎となる部分を作られるわけですから、安全性などにも気を配られたのではないですか。
I−
例えば、平台の角が尖っていたら役者が怪我をするだろうとか、継ぎ目をなくすようにとか、舞台から楽屋への導線は段差をなくすとか、どのぐらいの高さならクリアできるのだろうとかね。そうしたことには、随分気を遣いましたね。
T−
そういえば先日[-IST]にて拝見したイラクの劇団は出演者のほとんどが裸足でした。舞台に上がる時、役者の方は無防備な格好になりますよね。
I−
彼らはそのまま暗転の中を移動するわけですから、できるだけ安全な状態を確保してあげなあかんでしょう。しかもそれらが、1年で壊れてしまうのではいけないから強度もつけなくてはいけないのです。
T−そうした心配りは普段のお仕事の中で身につけられたのでしょうか?
I−
安全や強度に対する意識というのは普段の施設や住宅の仕事とあまり変わらないものです。私もこれまで仕事をしてくる中で、「もう1回確認しに行っておけばよかった」とか「打合せをしておけば」というようなイタイ目に何度も合っているんです。あほでも10年やれば分かる程度のことだけど、リスクや失敗に対する経験は積まれているかな。
T−
竹内さん自身も芝居をしておられたと佐藤さんからも伺いました。私には、先ほどから挙げてくださるとても具体的な事例がその証のように感じます。今回、以前劇団に所属しておられた経験が活かされた?
I−
そうやねえ、僕も芝居が嫌いなわけやないから今でもよう観にいくしね。僕もやりたいなあと思うこともあるもん。劇場をもちたいというのはないけど。
うちじゃないとできないというような、技術的に難しいということは別段なかったです。ただ、栃村さんとは昔からの知り合いで、ぼくも芝居の人間やったから、伝えたいことははっきり言えて密なコミュニケーションをとれるというのが重要だったのではないでしょうか?
T−
芝居を始められたきっかけというのは?
I−
芝居はね、やっぱりおもしろかったんやね。僕が早稲田大学に通っていたころは、学生劇が盛んでね。たまたま暇にしていて学校内をぶらついていたら、「こだま」という劇団にはいっている高校の同級生にばったり会ったんですわ。それで、彼に声をかけられて見に行ったのがはじまりですね。こんな面白いものがあるのだったら、ぜひやってみようと思って。
それまではどちらかというと文学青年やったからね。でも演劇は3日やったら止められへんというけどまさにその通りで。 状況劇場とかに影響受けていましたわ。 その後、「劇団 摩呵摩呵」という女優の銀粉蝶などと同じ劇団で制作をしていました。野外でやる方がどちらかというと多いような劇団だったし、僕も建物内の劇場にこだわるというよりも、おもしろい演劇空間をつくり出したかった。
T−
先程、通常のお仕事として今回の依頼を受けるのは社長としては許されへんとおっしゃっていましたが。
それでも、協力なさったのは、そうした竹内さんなりの演劇への想いがあったからですか?
I−
そういう仕事を社長が取ってきて社長が受けているという、いちい工芸としては非常にまずいですな。
最初に相談があった時に[-IST]の方とはいろいろ話したんですわ。その中で、関西の小劇場、扇町ミュージアムスクエアや近鉄小劇場がなくなった今だからこそ、やりたいという情熱を伺って、なかなか説得力がありました。
僕が演劇をやっていた頃というのは70年代です。アングラが十分に力をもっていたこの時間帯に遭遇してきた世代としては、栃村さんなどが自分達の劇場つくっていきたいと思う気持ちが分かるんですよね。
そういう、いろいろな人が集まって、ちゃんと表現に遭遇できる場所ができるということは、やっぱり嬉しいわけですわ。まあ、とにかく一番は「おもしろい」芝居を見たいです。
T−
やっぱり、芝居の世界から今のお仕事への転向、変わられることに抵抗はありましたか。
I−
しかたないよね。継がないといけない状況があったもので。昔から僕は不器用やったしね。あんまり仕事は好きくないねぇ。給料もらわなあかんからやってますけど…社長やと責任も重いしね。
仕事の達成感というものからくる充実はあるかもしれないけれどね。仕事ってどうしてもお金がついて回るでしょう。自分のすることがお金に変わっていくことが好きな人にとっては、それは楽しいことかもしれないけれども、苦手な人間にとってはしんどいよね。
誰かが仕事を上手く運んだら、誰かが困るという図式が必ずあるじゃないですか。みんなが分相応というわけにはどうしてもならないからね。まあ、あんまりこんなことを考えない方がいいですよ。
T−
劇団にはそうしたことがないのでしょうか。劇団にいたころの責任とはちがう?
I−
座長とかなかったけど、劇団にいても責任はありますよ。でもそれは全部自分達でつくりあげなくてはという意気込みみたいなもんだからね。僕らが劇団をやっていたころなんて、衣装もメイクも大小道具も全部自分らで作り上げなあかんかったからね。こんなん言ったらあれやけど、今の劇団の状況はぼくらから見たら天国やね。どの劇場にいっても舞台監督さんがいて、ゲネプロ(*2)もちゃんと仕切ってくれるでしょう。
T−
過酷な状況であっても、作ることが楽しかった?
I−
楽しかったかと聞られればつらいことの方が多かったかな。例えば、交通費が無くてリヤカーで道具を運んだり、コーラの空き瓶を拾ってきてそれで飯代つくってたとか、それで稽古にでられなかったりとかね。
|
|
|

|