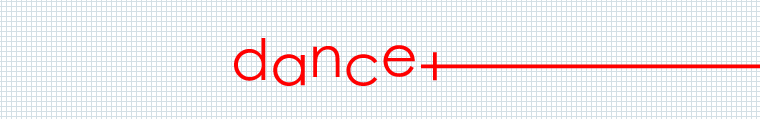
| 日々是ダンス。踊る心と体から無節操に→をのばした読み物 |
|
|
|
|
+舞踏の方たちは金粉ショーでもって、いろいろな舞台、お客さんを経験されたのですね。キャバレーの全盛期から衰退期、その中でストリップ劇場とか。
大谷:そうですけれど、踊るということについての意識はあまり変わらなかったですね。キャバレーで踊ろうが、劇場で、いわゆるアートというジャンルで踊ろうが。そりゃ踊るものは違いますけれども、やっぱりキャバレーで鍛えられているので、客に対して自分をどう見せるのかっていうことに対して、キャバレーで踊っていた人たちは非常に意識が鋭いですね。今でも、舞踏で当時キャバレーをまわっていた人のダンスを見ると、非常に面白いです。これは、言ってしまえばエンターテイメントの意識が体の中に入っているのでしょう。それがキャバレーを廻ったことの強みやと思うし、そういう意味で僕の経験上も、踊りの感覚っていうのは、本当に変わらないですね。ただ違うのが、劇場での舞台だったら1年に2,3回、多くても8回くらいしか踏めないけど、キャバレーは、女の子なんかだと1年に280日くらい踊れたという点ですね。
あと、ギャラとしても30年くらい前でも1日行って手取りが1万5千円くらいありましたもんね。例えば金粉ショーの3人パッケージで、『エロスパンドラ』っていうのがあったんですが、-金粉ショーは、女の子1人入れておけば男2人とも行けるんで、結構男の稼ぎ場としてはあったんですよ-それで3人行って4万円強ありました。だから、今でも大駱駝艦とかすごく舞台に凝ってお金をかけていますけれど、舞踏のグループが、当時から非常に舞台にお金をかけたのは、キャバレーで稼いだお金を舞台につぎ込めたからなんですね。そういう意味でいうと、本当にキャバレーで稼いで舞台にお金をかけるということをしていました。
+男ばかりの山海塾は金粉ショーができないのでは?
大谷:ええ、山海塾としてはやっていないと思いますが、天児さんはバリバリやっていましたよ。天児さんは金粉ショーすごく好きな人で、5人のパッケージで『カーマスートラ』って言うんですけれども、すごく廻ってましたね。振り付けは僕の師匠のビショップ山田っていうのが始めは作っていたのですが、彼が忙しくなってくると、その次に踊れる天児さんがそのパッケージショーを仕切っていた時期がありました。それで彼は、ショーでキャバレーを廻るという方法を、そのまま山海塾に移したんですね。正式に旗揚げする前の半年くらいのことですが、ヨーロッパに行く前に、日本国内の大学祭をああいったかたちで廻っていました。それは男ばっかり。たぶん資金的には、今日本でやるのは大変やろうなと思ってはいたんですが、あんな風にヨーロッパに行って成功して。
+その後、ショーで廻る場所がなくなってくると、今のようにダンスでは稼げないという状況になってゆくわけですね。
大谷:面白いのが、キャバレーが廃れると同時に、芸術文化振興基金みたいなのが出てきたことなんですよ。例えば大駱駝艦なんかでも、今文化庁の21世紀アーツプランかな、そういった助成を受けて公演を打ってますけれども、キャバレーのない今、助成がなかったら公演は難しいでしょうね。
+アートが保護の対象となったような印象を受けますね。それ以前は、劇場以外に踊る場所が実はたくさんあって、自分たちで流通経路を作っていけたのですね。
大谷:そのときに金粉ショーというツールを発見したというのは、非常に大きいよね。
竹ち代:うんうん。
|
|
|

|